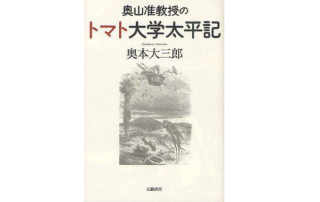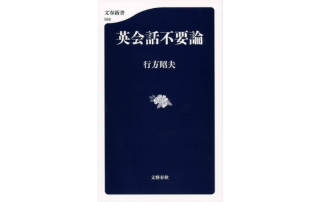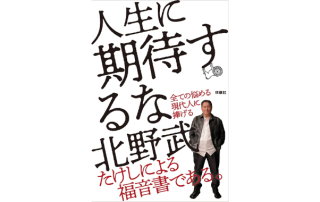『奥山准教授のトマト大学太平記』(奥本大三郎著、幻戯書房、2011年)
評者:石井 恭平(ヴェリタス英語科講師)
第一節:とある大学教授の日常を題材にした小説
これまで私が書いてきた書評を読んだことがある方には、もはや隠しきれなくなっているかもしれない。私は天邪鬼である。これまでの人生でも、これからの人生でも、有名本の書評を書くことはできるだけよそう、と固く決意している。今回私が選んだ本も、おそらくは、あまり世間では知られていないだろう。「とある大学教授の日常を題材にした小説」というジャンルであれば、筒井康隆氏がものした『文学部唯野教授』(岩波文庫、1990年)などが有名であり、この本を挙げる人はあまりいなそうである。私は、あまり知られていない本や、読むべきでないとされている本のなかで、とても面白かったものを「ゲキシブ本」と呼称しており、こうした「ゲキシブ本」の中で、よく読むと興味深いことが書いてある部分を引用して褒めちぎるということをしばしばやってきた。私がこの本、『奥山准教授のトマト大学太平記』と最初に出会ったのは相変わらず東京都北区の区民図書館であるが、タイトルの意味不明さに惹かれて最初の章を少し読んでみたらあまりにも面白く、ネット上で191円で売られていたので、すぐに購入してしまったのである。私はいわゆる「小説」を読むのも嫌いだし、難しい「学術書」を読むのもどちらかといえば嫌いなのだが、そんな私でもスラスラと読めてしまう「学術的小説」というものが世の中には存在しており、それを読むのは本当に楽しかったのである。「学術書」と「小説」を日頃からあまり読まないのであれば、「学術的小説」はもっと読めないに違いないと思ったら、そうではなかった。このことを私に教えてくれた本がこの本である。
この本を読むと、プルーストやユゴーといったフランス文学史上の英傑たちのナマの文章に、フランス語原文も織り交ぜながら、触れていくことができ、「なるほど、こういう点に注目して読解していけばフランス文学はこんなにも面白く読めるのか」ということを学ぶことができる。ただし、「学ぶ」と言っても、堅苦しく学ぶのではない。変人教授の突拍子もないカマシや韜晦、冗談、謎かけがずっと続いていく、そんな小気味良さのなかで、気づくと知識がもはや自分にとって疎遠なものではなくなっているのである。読者は、学んだという自覚もないままに、学びの過程がもはや終了していることに気づくのである。
この物語の主人公である奥山万年准教授にそのような教育的意図や、教育方法論上の秘技の自覚があるかについてはよくわからないのだが、私はこういう教授の話し方に、研究者・教育者・対話者としての模範を見ることができるとさえ思っている。もちろん彼は、発言を読む限り、自分のことを(良き研究者だとはさすがに思っているだろうが)、良き教育者であり良き対話者であるとは微塵も思っていなさそうである。しかし、そのような自己規定に「居着く」ことで、偉そうにふんぞりかえるだけの権威者が多いことをも考慮するならば、まさにこういう自己規定を持たないで飄々としていられることもまた、良き教育者であり良き対話者であるための条件だとさえ私は言いたくなる。以下では、(1) 奥山准教授とはどういう人か、(2) 奥山准教授の言語感覚、(3) 奥山准教授の教育実践という三つの観点から、この本を分析していきたいと思う。(以下、特に記載のない限り、引用は全てこの本からであること、紙幅の都合で改行を省略した箇所があること、強調のための太字は私によるものであることを、あらかじめ断っておく。また、前回の書評と同じく【隅付き括弧】の中は、私が引用部にタイトルをつけたものである)。
第二節:奥山准教授とはどういう人か
奥山准教授は、とある国立(現在は半独立行政法人へと切り替えられた)大学の仏文科の准教授であり、研究予算の削減に苦しめられている。フランス文学を学びたいと言う学生は年々減っており、仏文学生の就職難もあり、「そのうちオーバー・ドクターの中からホームレスが出るよ」(40頁)などと言われても、特にできることはない。そういう状況で彼は地道にフランス語、そして「落日のフランス文学」の魅力を学生に伝えようとし続けるのである。その教え方については後の節で見ていくとして、このひとの人柄がたいへん面白い。以下の引用を見てみてほしい。
引用1.【奥山先生はひとりで電車にも乗れない】
「実は今日、先生はあやうく遅刻するところであった。新学期だから、とずいぶん早めに家を出たのだが、電車の中で本を読み始めて駅を乗り越した。慌てて反対ホームに来た電車に乗ったのはいいけれど、本の続きを読んでいて、またもや乗り過ごしてしまった。さすがにこれではいけないと思ったか、今度はずっと立って吊り革につかまりながら景色を眺めていたが、あいにくその電車は次の駅どまりで、ホームに降ろされてまた次を待たねばならなかった。どうもこの先生は事務能力が欠如しているのみならず、社会生活全般にわたって不適応のようである。おまけに空想癖がある。これから大学に行って大切な講義があるというのに、やっと乗った電車の窓の外に桜が咲いていたりすると、「ああ、今頃、富山か新潟の山里に行くとギフチョウが飛んでいるだろうなあ⋯⋯」と、菫や片栗の花を訪れて、ぶら下がるように蜜を吸っている、黄色と黒の小型のアゲハチョウの姿を思い浮かべる。杉林の林縁のそよ風まで肌に感じているような気になって、また乗り越しそう。まったく、ひとりでは電車にも乗れないような男なのである。」(42-43頁)
引用2.【ドルチェ・ファル・ニエンテ(甘くしてかつ無為)】
「某月某日、先生は昼頃になって起きだしてきた。実は朝の十時頃に一度目が覚めたのだけど、一言、「Liberté!」とつぶやいてまた寝てしまい、やっと今、いくら何でも、もう眠れなくなって起きたのである。「Liberté」とは、フランス語で「自由よ!」と女神に呼びかけたつもりなのであろう。休みになっていつまでも寝ていられる境遇をありがたがっているのらしい。奥山先生としては当分何もしなくていい、借金を取り立てに来る人間もいない、食い物はすぐ近所に売っていて、それを買う金もある。更に言えば、国が戦争をしているわけでもなくて、外国からの空襲もない、特高警察につけ狙われてもいない、なんとありがたい境涯であろうか、と思って「自由よ!」とつぶやき、また寝たのである。昨夜、フランス・レジスタンスの詩人の作品や、大杉栄の『獄中記』なぞを読み散らかしたのがいけなかったらしい。こういう人間を昔から「太平の逸民」といっている。」(105頁)
引用3.【鬱憤を晴らすメント】
「奥山先生は学生に「おーい、箒買ってきてくれー」と言って金を渡す。この研究室ではそれで通じる。憂いを払う玉箒、つまりお酒である。ボードレールはその散文詩集の表題を『パリの憂鬱』Le Spleen de Parisと名付けている。spleenは英語で、「憂鬱」。ボードレールの英国趣味(アングリシスム)である。それに倣ってか、Chasse spleenという銘柄のワインもある。chasseは「追い払う」ということ。先生はこうやって学生相手に酒を飲むことを「鬱憤晴らすment」と呼んでいるが、「スプリーン」とはもともと脾臓のこと。古い西洋の解剖学では、憂いは脾臓に宿る、と考えられていたのである。とはいえ、アルコールで脾臓を壊しては先生大変、などと誰も心配はしてくれない。学生も一緒に結構楽しく飲んでいる。」(51-52頁)
端的に言おう。奥山准教授は、無為を愉しむひとである。「引用1」では、窓から偶然見えた桜やそれが連れてくる想像がもう既に彼を喜ばせている。「引用2」では、切迫してやるべきことがなく、空襲も特高警察もいないというそのことを彼が無上の価値としていることがわかる。こういう態度が唐突に、そして割と詳細に描かれる章があることに面食らうひともいるだろう。しかし、よくよく考えてみると、そもそもは「妻とのんびりデートをするために仕事を始めた」はずが、「仕事をこなすためには、妻とのんびりデートに行く時間が邪魔になる」というような転倒が生じてきて、最終的には離婚したりするのが現代人である。我々は奥山准教授のスローな暮らしぶりに見習うところが多いのではないかと思わされる。
そして、「引用3」からは、奥山准教授がどんな時もユーモアを絶やさぬひとであることがわかる。全編にわたり、奥山准教授はこの調子でふざけ倒している。私もかつて、仏文科に在学していたことがあり、ブリア=サヴァラン(1755-1826)という美食家の批評文をフランス語で読んだあと、授業中に教授が「では、実際に飲んでみますか」とか言ってそのまま試飲会へと転じていったことがあるが、こういう授業が本当に楽しかった。学生と教授が和気藹々と話しながら知的な議論を進めていき、どんな話も軽視されずに、知的世界への入り口にしてもらえるのである。五感をフルに使いながら、軽妙な言葉に笑いながら、酒の肴だと思っていたものも気づくと学問の入り口だったことに気づく。「シンポジウム」の語源が酒を酌み交わしながらの知的談義であることを考慮すれば、こうした授業は逸脱的であるどころか学問の本流であると言わざるを得ない。やり方さえ間違えなければ、宴会と学問は両立するどころか相乗効果さえ生むと奥山准教授は思っているのではないか。
ただ、とはいえ、奥山准教授はいつもふざけていると見せかけて、ときどき次のような鋭い発言を行う。そのことによって、学生を一気に思考へと誘う。そうした箇所も少しだけ見ておこう。
引用4.【後発組のキリスト教は、先発組の自然信仰を利用することで栄えてきた】
「ローマ=カトリック教会は時間をかけて、古い迷信や、異教の神々が引き起こすと信じられていた超自然の出来事への信心を、キリスト教の奇跡への信仰に変え、聖人たちへの崇拝に置き換えたんだ。復活祭なんか、冬の間弱っていた太陽が春になって蘇ることへの喜びの祭りだったのが、キリストの復活を祝うものに置き換えられたわけだろ。」(138頁)
奥山准教授は「ケルト教」と「虫」にものすごく詳しい。神秘を言祝ぐ地元土着の自然信仰を「実はそれはキリスト教の神の力を授かった聖人によるものだった」という論理が包摂していくさまを彼は描き出している(同書の第四章を参照)。その章で奥山准教授は「引用4」のように語る。本論から少し逸れることを承知で、この件について少し私も自分の頭で考えてみたい。
実際、我々の日常には不思議が満ちているのではないか。金沢市で、自分も元ホームレスだった経験がある坂優(1947-2018)氏は、晩年になっても、「動けなくなるまで」ホームレス支援をしていたという。その一方で、一生かかってもひとりでは使いきれないほどのカネを持った政治家や財界人が「再分配など言語道断である!」などと高らかに言ってのける。不思議である。簡単そうなことはそう簡単には起こらず、難しそうに見えること、まず起こらなそうなことが意外にも起きている。なぜだろうか。なぜ貧しい人が他人を助けるのか。助けることを歓んでさえいる。それは、「貧しい人こそ神に近く、人はそもそも神の似姿だからであり、神の恩寵が彼に助力しているから」なのだろうか。むしろそのような理屈はこの神秘を合理化するために後づけされた理屈であって、実際にはもっと地に足のついた次のような論理がありそうである。
「誰かに助けられた貧乏人は、その誰かから受けた愛が自分の所有物によるものではないことを理解するだろう。なぜなら、所有物など彼には元々ないからである。だから、所有物なき所有者それ自体へと向けられた愛は彼に直接届き、所有物がまたなくなっても、末長く持続する。この持続的な安心を背景に彼は所有物を手放せるひとになる。それに対して、所有物を理由に愛されたことしかない人間はこの不安を背景に、所有物を手放せないひとになるのである。」
では、これで神秘の帳は解かれたのか。否である。私がいまこしらえた上記の論理でさえ、「誰かが見返りを求めずに、困っているひとをそのありのままで愛した」という最初の神秘を前提して放置している。我々が自己犠牲をするなかで、各個体に伏流するより大きな力に合流していくような歓びを味わうことがある、これを事実として私は追認するしかない。こうした利他行動とその延焼という神秘が日常のなかにはあり、それを合理化する理論装置として作られたのが神である。平たくいえば、「それを起こす神がいるから神秘が起きるのではなく、神秘が起きるからそれを起こす神がいることにされる」のである。
自然についても話は同様である。どうしたら光合成は再現でき、どうしたら細胞や脳で起きていることを解明でき、どうしたら地震を予知できるのか。重力や光なるものも正直、理解不能だが、植物はそのふたつの情報をどう処理しているのか。電子に体積はあるのか。時間と観測者との関係はどのようになっているのか。地球外で、いつもの化学反応はどうなってしまうのだろう。調べれば調べるほど謎は深まる。根本的なことは、ほぼ何も分からないまま、日々自然は神秘を次々に生成し続けている。こうした神秘を一身に担当して合理化する都合のいい神様を仮設することも不可能ではないが、まずはそのような仮設に先立って自然それ自体が神秘の塊であり、一番手の存在であるというこの順序は動かない。
第三節:奥山准教授の言語感覚
奥山准教授は、言葉に(そしてその音や語感にも)敏感である。この小説を通して彼はずっとくだらない言葉遊びをし続けようと意識していることからもそれは明らかであるが、しかし、その技術はもはや、「ダジャレなんてくだらない」と一蹴できるレベルを超えている箇所が散見される。例えば、旧約聖書の『ルツ記』から着想を得たヴィクトル・ユゴーのあまりにも美しい詩「眠れるボアズ(Booz endormi)」を解説する際、« Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth »という行の中の都市名ウルはいいとして、「Jérimadeth(ジェリマデ)」はどこを探しても見つからない。読者は一瞬戸惑うだろう。しかし、奥山准教授は、« j’ai rime à dait (=私は「デ」で韻を踏む) » が隠されていると言って言葉遊びを見抜くのである(102頁)。実際、その直後、ユゴーは「demandait」で脚韻を踏んでいる。こうした言葉遊びを笑いつつ、ユゴーの詩を解説していく手捌きは実に楽しく、詩を読むとは、実は無味乾燥なものではなく、音やリズムを味わうことと不即不離であるということが自然に読者に伝わる効果的なものとなっている。ところでこのユゴーの詩は、内容も面白い。「生の根源に立ち戻りゆく老人は、永遠の命のほうに入ってゆき、移ろいやすき日々からは離れてゆく。若者の目には焔が、しかし老人の眼には光がある」。なんとも意味深長な詩句ではないか。
他にも、奥山准教授は、次のようにして、昔の文人たちが言葉の選び方に細心の注意を払っていることを明らかにしていく。次の引用を見てみよう。
引用5.【ネルソンと東郷の頭韻による絆】
「「とにかくね、明治の人は必死で頑張ったんだよ。「皇国の興廃此の一戦にあり」って、誰の文句だ?」
「何か聞いたことありますね」
「聞いたことある、は冷たいんじゃない?東郷平八郎だよ。明治三十八年の日本海戦で、ロシアのバルチック艦隊と戦う時に東郷元帥が発信させたZ信号旗のシグナル。このあと「各員一層奮励努力せよ」と続く。口に出し
て言ってごらん」
「口調がいいですよね」
「うん、Kou koku no kou hai kono issen ni ariと、kの頭韻が踏んである」
「これから戦争するという時に、ヨユーですね」
「余裕か。いや、逆に緊張感を高めるというか、土気を鼓舞する。これが「サーイクヨー、ガンバッテネー」じゃ、戦にならない。君ならどう言う」
「さあー」
「実は東郷元師がこれを発したのには、前例があるんだ。トラファルガーの海戦って世界史で習っただろう。英国の艦隊とフランス、スペインの連合艦隊がスペイン南西トラファルガー岬の沖で戦った。一八〇五年、日本海海戦のちょうど百年前だ。これを率いたのが彼の有名なネルソン提督。もし負ければ英国はナポレオンに征服される、という国難の時だ。まさに「皇国の荒廃⋯⋯」という一戦を前にして、ネルソン提督は信号を発する。Z旗と同じで、マストに旗を掲げて信号を送るんだよ。England expects every man to do his duty. どうだ、これはこのeの頭韻だ。東郷元師は英国に七年も留学して海戦を学んでいるから、当然これを知ってたわけだね」(89-90頁)
引用6.【「上田敏の秋」は「ヴェルレーヌの秋」が日本風に魔改造されたもの】
「上田敏は“秋の日の/ギオロンの/ためいきの/身にしみて/ひたぶるに/うら悲し”と訳したわけだけれど、原詩を見ると、“ためいき”とか“うら悲し”と訳すべき言葉はどこにもないね。sanglotsは、“すすり泣き”とか“嗚咽”に当たるよね。“秋のヴァイオリンの、いつまでも単調に繰り返されるそのすすり泣きのような音が詩人の心をblesserする”、つまり“傷つける”、あるいは“苦痛を与える”、というんでしょう。もっと直截に、心臓を傷つけるといったほうがいいくらいで、“うら悲し”とはほど遠いと思うよ。“うら悲し”というような、感傷的で、けだるいような、ものうい感じ、むしろ快いぐらいの甘い感じではない。もっとずっと悲痛なんだ。だから、“秋のヴァイオリン”は季節そのものの音、つまりビュービュー吹く北風の音だろうよ。それが何時までも単調に繰り返されて、止むことがないわけだ。身も心も死ぬほど寒い、やっぱり日本とは気候風土が違うんだ。でもこれをそのとおりに訳していたら、明治の日本であんなに人口に膾炙しなかっただろうと思うよ。日本的に甘く感傷的にしたのがやはり、上田敏の腕と言うべきでしょう。[…]そうそう、最後は、“ここかしこ/さだめなく/とび散らふ/落葉かな”とぴたっと止めてるだろう。この見事さ、鮮やかさ。これはまさに俳句の世界なんだ。こうなるともう、西洋の詩にヒントを得た洋食風の詩、というよりは和食だね。俳句では物というか名詞を提示して、それにすべてを象徴させることがよくあるじゃないか。たとえば“古池やかわず飛び込む水の音”という句を英訳してごらん。“水の音”で終わったんじゃ、外人は、きっと「水の音がどうしたんだ」と言うだろうよ。この訳詩でも一枚の落葉が、最後に接写レンズ的にクローズアップされて、詩人自身と秋という季節、そのすべてを象徴しているわけだ。」(190-191頁)
「引用5」は一見無関係に見えるものが「頭韻」に注目することで関連して見えてくることを垣間見させてくれる箇所である。「引用6」はさらに興味深い。上田敏(1874-1916)が翻訳した「落葉」といえば、日本でもたいへん有名な詩である。しかし、奥山准教授は、この翻訳が「死ぬ」ほど寒くなりうるフランスの秋、実際に「morte」という言葉で終わっていくポール・ヴェルレーヌ(1844-1896)の原詩が描いた秋を、「日本風の秋」へと大胆にも作り変えるなかで生まれたものであることを明らかにしていく。この箇所は、翻訳を少しでもやったことがある人なら、誰でも唸らされるだろう。翻訳という行為が実は創造行為でもあるということをこの一節を読むだけでも実感することができるからである。
第四節:奥山准教授の教育実践
奥山准教授は、本人は気づいていないようなのだが、教育がものすごく上手い。学生とおしゃべりしているうちに学生の興味をみるみる引き出す。次の一節を読んでいただきたい。例外的に長い引用となるが、奥山准教授がたったひとつの話題から様々な学問分野へと話を展開していくところを目撃していただくためである。どうか御寛恕頂きたい。
引用7.【対話型教育の模範となるような事例】
「「英語の肉の名前は、フランス語と似てますね。」
「というより、フランス語起源なんだね。」
「えー、ほんとですか。でも、どうしてなんでしょう。」
「どうしてだと思う。世界史で、ノルマン・コンクエストって習わなかった?」
「そういえば、聞いたことがあるような。ノルマン人って、ヴァイキングのことですよね。」
「そうそう、北欧のヴァイキングがね、冬になると畑仕事ができないもんだから、船に乗ってフランスに攻めて来たんだ。セーヌ河をさかのぼって沿岸の街を略奪する。いわば農閑期の出稼ぎだけど、しまいにはパリにまでやって来て猛威を振るった。連中は武力に優れているんだよ」
「ヴァイキングは、どうしてそんなに強いんですか」
「第一に身体がでかいし、もともと寒冷地に住んでいて貧しいから必死なんだ」
「でも、どうして身体が大きいんですか、食べものは貧しいんでしょ」
「それはね、“ベルグマンの法則”というものがある。「同じ仲間の哺乳類において、北に住むものほど身体が大きくなる」というものでね。トラを見ると、スマトラのトラとシベリアのトラとでは倍ぐらいシベリア産のほうが大きいし、クマだと、マレーグマ、ツキノワグマ、ホッキョクグマと順に大きくなる。これは、身体が大きくなると、体表面積が相対的に小さくなるからなんだ。寒いところに凄むものほど、体格の大きいほうが有利というわけ。北欧は寒いから人間もでかくなるんだ。それで強い。それはさておき、ヴァイキングの被害があまりに大きいんで、フランク王国の王様はたまりかねて、とうとう九一一年のこと、ノルマンディー半島をヴァイキングの大将のロロという人物に頷土として与えるんだね。このロロなんて金髪の大男で、馬に乗ると脚が地面につかえたと言われている。これが初代のノルマンディー公爵だ」
「貴族といっても、もともと育ちがいいわけじゃないんですね」
「そりゃそうさ。最初は、いわば強盗団の首領だよ。でも二、三代も経れば立派な貴族だ。そもそも、ノルマンディー半島という名前もノルマン人に由来するわけで、Normand つまりNorthman だね」
「へえ、そうですか」
「そのノルマンディー公のギヨーム、英国式だとウィリアムという男が、一〇六六年にイギリスに攻め込んで、「ヘースティングズの戦い」という決戦で勝利を収める。「バイユーのタピスリー」という織物にその様が描かれているけど、元ヴァイキングがとうとうイングランドの王様になってしまうんだ。それが、征服王ウィリアム一世というわけ。このウィリアム一世という男は、知謀に富むというか、機転のきく人物でね。イギリス征服の船から上陸した際、足がすべって腹這いに転んだんだ。「あっ、縁起が悪い!」と部下の顔が青ざめた時、悠然と立ち上がって、「なに、これから我らが物となる土地にキスしたんだ」と言ったという」
「転んでも只では起きない、とか」
「で、問題はだね、ヴァイキングがノルマンディー半島に住みついてるうちに、すっかりフランス化してしまっていたことなんだね。連中は、武力はあったけれど、文化程度は劣っていたから、言語も風習も、初代の口口から七代百五十五年のうちにすっかりフランスかぶれというか、フランス人そのものになってたんだね。それがイングランドを乗っ取ったもんだから、イングランドの宮廷ではフランス語を話すことになってしまった。そもそも形式から言うと、その英国王はフランス王の臣下ということになる。そんなわけで、英語に大量のフランス語の単語が混じることになった」
「征服された方、というか、英国の地元の人は、元々の英語を喋っているわけでしょう」
「そうだよ。アングロ・サクソン人と言われる人々は、元来の英語を使っていたわけさ。そこにフランス系の単語が大量に混じっていく。それで、英語とフランス語の語根の八割が共通のものになった。もちろん、その大本はラテン語だけどね。英語の辞典で語源のところを見ると、“ノルマンフレンチ”とか書いてあるよ」
「それでですね、家畜の名前と、その肉の呼び方ですけど⋯⋯」
「つまり、生きてる家畜の名称は、平民というか農民の言葉なわけでしょう。cowとかsheep とか言ってる。彼等が飼って世話をするんだ。だけど、その肉を食べることができるのは貴族だけだよ。だから、フランス訛りでbeef とか mutton とか言う」
「なるほど、そういうわけなんですか」
「君、焼肉好きか」
「好きですけど⋯⋯急にどうしたんです?」
「ハツ、タン、ガツ、レバなんて注文するよね、これは元々、何語かね」
「え、考えたことなかったけど、ひょっとして韓国語ですか」
「どうして」
「だって、韓国焼肉って言いますよね」
「いや、英語なんだ。ハツがheart、タンがtongue、ガツがgut、レバがliver だ。酒を飲み過ぎたりして肝臓を悪くすることを、レバイタメと言うじゃないか。」
「言いませんよ。でもさっきの英仏語の関係を適用すると、日本はアメリカに征服されたんですか。」
「君もハッキリ言うねえ。でも、まあ、実際そんな感じだなあ。日本人は肉食に関しては歴史が浅いというか、昔は内臓の旨さを知らなくて捨ててたから、“放るもんや”ってんでホルモンになったと言うけどね。“心臓焼いてくれ”、“肝臓生で食べたい”じゃ、日本人の感覚では生々しいから、わざと英語使ったんじゃないかね」
「わざとですね」
「英語が普及する前は、音読みにした。つまり、漢語風にして感じをやわらげたのかな。生きてるとウシで、肉はギュウだろ。鶏は茶褐色の羽の色から、枯れた柏の葉を連想したんだろう、昔から「カシワ」と言ってきたし、猪の肉は「牡丹」、鹿肉は「紅葉」、馬肉は「桜」と、まるで符牒だ。生き物を直接連想させることを忌んだんだろう。それまでの日本人が日常食ってたのは、雑殻を混ぜた飯と菜っぱとたくわんと味噌汁だ。」(奥本大三郎著『奥山准教授のトマト大学太平記』165-169頁)
お分かり頂けただろうか。「引用7」には、冗談も混ざっているが、実は出現順に並べてみると、❶食文化、❷世界史、❸地理学、❹進化生物学、❺語源学、❻婉曲表現といった、さまざまな学問領域を次々と横断しながら、着実に学生たちは英語とフランス語の複雑な関係を(「ただ似ている」という表面的な仕方ではなく)、根本的に理解していくのである。こういう「根源性」と「俯瞰性」を両立させた話し方のできる気さくな先生がフィクションのなかの主人公ではなく、本当にいたら、大学生活はどんなに楽しくなるだろうかと私は思わされた。
さて、本書評では、第一節で予告したとおり、三つの観点から手短にこの本の魅力を分析してきた。そろそろこの書評も終わりにしなければならない。この小説のあっと驚く終わり方などについては、ぜひ読者の皆様がご自分の目で確かめて頂きたい。
石井 恭平
『英会話不要論』(行方昭夫、文春新書、2014年)
評者:石井 恭平(ヴェリタス英語科講師)
第一節:読み書き偏重、上等論
私は文京区本郷にあるヴェリタスという塾で英語を教える仕事をしている。授業スタイルそれ自体は、さして変わったところもない。誰にでもすぐに分かる明快な構造の授業設計ばかりをしている。まずは英文で書かれた難しい文章を用意し、毎週担当範囲を決めて参加者に、①訳出してもらい、②文法解説と、③内容解説までしてもらっている。①訳出→②文法検討→③内容検討というループを教室内に発生させ、全員で発表者に質問をしながら回しているのである。そして①→②→③のループを何度も何度も繰り返す。たまに脱線で与太話が生じたり、適宜、英語文法復習タイムを設けたりもしているが、基軸となるのはこのループだけである。そして、④英作文の課題を毎週、お題を決めて提出してもらっており、私がコメントを書き込んで返却していく時間もとっている。いま①②③④と書いてみて驚いたのだが、文字にすれば数行で済む、こういう授業である。これをいま、私たちは毎週やっている。余計な意匠を排したこういう授業は、やっていて気づいたのだが、意外に奥が深いらしい。というのも、私の授業には固定化された上下関係というものがない。上下関係を生じさせられるほど、子供たちから見て尊敬できるような点が私には皆無だからというのも理由の一つだろうが、それよりもむしろ、欠席者のぶんの担当範囲は私が引き受けて発表していたり、子どもたちに混ざって私が質問をすることも多いがために、私の役割は、多く見積もってもゲームマスター役、オーガナイザー役、ファシリテーター役でしかないからである。「授業をやる側と、それを聞いていて質問する側」という対立、より抽象化して言えば「能動と受動」という伝統的な二項対立も、ある仕方で現れたと思ったらやがて解体されていき、すぐにまた別の仕方で現れるのだから、あくまで動態的にしか存在しない。「こういう授業はエクリチュール(=書くこと、書かれたもの)の分析にあまりにも重心を置き過ぎてはいないか、すなわち「読み書き偏重、文法偏重」では時代に置いていかれるのではないか」という批判が寄せられるだろうから、それに応えたいと思っていた矢先、私はある本を手に取った。その本とは、行方昭夫著『英会話不要論』(文春新書、2014年)という本である。アマゾンで中古が「1円」で売られていたからというのもあるが、鮮烈なタイトルと著者名に惹かれたという方が、購入理由を述べるには適切だろう。というのも、良質な英語精読書をたくさん出してきたことでよく知られている行方昭夫氏に、私は北区中央図書館で英語の勉強をしていた時分、本当に救われてきたからである。私は、行方氏の本を無料で借りて、何冊も読んできたけれど、この本を読んだことはなかったので、この書評執筆を機に読んでみて、つくづく思い知った。行方氏の文章の魅力は、金儲け主義者の口八丁手八丁には決して惑わされず、エセ学説の痛いところを突く鋭い観察眼であり、それはつまり、魅力的な学説に飛びついてリアリティを見失ったりしないところである、と。つまり、浮華を去った、摯実な批評眼が、氏の文章の隅々にまで浸透していたのである。こうした分析力が、氏も自ら言う通り、長年の難しい英文読解の仕事の賜物であることは、私のような若輩者にも容易に伝わることである。しかも、氏の文章にはユーモアがあって、読みやすい。冷静な筆致なのに、時々クスクスと笑いながら読める文章というのは、いつまででも読んでいられる文章だと言えるだろう。
以下、本書評では、この本からの引用を紹介していきたい。行方氏は、先述した「読み書き偏重」につき、次のように述べている(以下、特に記載のない限り、引用は全てこの本からであること、紙幅の都合で改行を省略した箇所があること、強調のための太字は私によるものであることを、あらかじめ断っておく。また、前回の書評と同じく【隅付き括弧】の中は私が引用を要約したものである)。
引用1.【ネット時代には読み書きも役立つ】
「日本で「役に立つ英語」を教えるべきだ、というのは、話し、聞く能力を伸ばす教育を指しているのです。英語を読み、書く力がついたならば、それも「役立って」いる筈です。それどころか、インターネットや電子メールの時代では、海外とのやり取りには、むしろ「読み、書き」のほうが重要だといえるのです。」(20頁)
引用2.【文法偏重こそ近道である】
「文法と聞くだけで頭が痛くなる人もいますが、英語のように言語構造が日本語とまったく違う言語を使用する場合、英語非母国話者なら文法を知らずに、言葉を組み合わせて喋ることなど不可能です。」(26頁)
引用3.【ハンバーガーの注文は後回しでよい】
「昨今、文法、訳読軽視のため、英語学習者の一般の読み、書く力が低下してきました。たとえ英語でちょっとした挨拶やハンバーガーの注文ができるようになったとしても、その代償は余りにも大きいのではないでしょうか。」(28頁)
引用4.【書けないことを話せるわけがない】
「話したいことが頭にあって、それを口で言う場合、それを書けなければ話にならないという事実を確認します。日本人の場合、初歩段階では、英作文力の向上ほど、話すのに役立つものはありません。」(74頁)
引用5.【目減りするペラペラの価値】
「国際会議の議長として成功する秘訣は、お喋りなインド代表を黙らせ、沈黙しがちな日本代表を喋らせることだ、というジョークがあるのを話すこともあります。」(76頁)
引用6.【読解が一番実用的である可能性まである】
「英語を読み、書き、聞き、話すという四つの能力の中で、ここでは「読み」の力の低下を見てきました。これが「話す・聞く」能力重視に英語教育の方針が傾いた結果なのかどうか、即断できませんが、残念なことです。というのも、一般の日本人がもっとも多く活用するのは、実は、この能力だからです。他の三つの能力を使う機会は、生涯で何度あるでしょうか?「書く」ことはあまりないでしょう。「話す・聞く」は、日本在住の外国人に接したり、海外に旅行した先で買い物したりする時くらいでしょうか。一生でせいぜい数回ではありませんか。一方、読む機会なら、広告であれ、缶詰などの説明であれ、頻繁にあります。」(95頁)
ここまで読んで、著者の舌鋒鋭さに驚く方もいるだろう。しかし、要点は伝わったはずである。要するに、読み書きにやたらこだわること、文法を気にし過ぎることは、実際には正しいアプローチだと言いたいのである。詳しいデータを引用していく紙幅はないから、もっと多数のファクトが欲しい読者は、ぜひこの本を手に取っていただきたい。しかし、常識を働かせてみても同じ結論に至れるだろう。もちろん、英語を喋れて損はないが、「引用2」と「引用3」と「引用4」からもお分かりの通り、英文法を駆使せずに話せることなどたかがしれており、定型句や挨拶ではなく中身のある主張を論理立ててしようと思ったら文法が必要になる。そして「引用5」が冗句として機能するとしたら、英語を流麗高速で喋れることが評価されるのは、日本国内でであって、国外でではないのかもしれない。もしも「ペラペラが役に立つ」というのが「ペラペラだと日本国内において英語の達人感を出すのに役に立つ」ということを指しているのだとしたら、外国語学習というものは本来そのような自閉した動機で起こったのではないということを思い出す必要があるだろう。私の家の近所には「プチメゾン」という建物があるのだが、このような「フランス語のように見える何か」を私の大学時代の友人だったフランス人は、写真を撮って集めていた。文法を無視してやたら外国語で話そうとしがちである傾向が私にもあるかもしれないので、気をつけたいと思わされた。
「引用1」と「引用6」が主張しているのは読解能力が意外にも多くの人にとって有用だということである。この件については「想像力」という重要な概念との関係で、節を改め、もう少し詳しく見ていこう。
第二節:読解訓練と想像力について
実は、読解し訳出する訓練は、日常生活の中で有用であるにとどまらず、人間が何か未知のものを理解するときに働かせている力、つまりは「想像力」を鍛えるというより広汎な意味での有用性へと通じているのである。ここでも、著者の言葉を引用してみよう。
引用7.【理解度は訳出させて初めて検出、評価、改善の対象となり得る】
「大学の入試で、英文和訳そのものが出題されなくなってきた理由には、もう一つの事情があります。他の章でも触れましたが、訳読という作業が嫌われ、時に「訳毒」などと称されているのです。英語教員の中にも、英文はそのまま訳さずに理解すればいいのであって、訳読など必要ない、と主張する人がいます。[…]訳すのを避けていた後輩の英語教員から、「理解度が怪しいので、今日は念の為に訳させてみたら、ほとんど分かっていなかった」という告白を、これまで何度も聞いたことがあります。理解度を確かめるためには、間に合わせのための、やっと通じるだけの日本語で構いませんから、とにかく日本語で言わせるのが、一番効率がいいのです。明治初期に英米人の教授からあらゆる科目を英語で教えられた新渡戸稲造などの英語名人たちが、放課後、念の為に教わったことを日本語で確認しあったというのは、賢かったのです。」(86-87頁)
引用8.【実用的でないという批判はむしろ批判者の想像力のなさを暴露している】
「Are you a boy or a girl? 「この疑問文が実際に使われる状況を想像してふさわしい日本語に訳せ」という問題です。これは、昔の中学一年用の教科書にあった文で、「愚かな質問だ。実際にはありえない」として非難されました。こういう質問を学生にしても、なかなか想像できないようです。そこで、私から、ロンドンに住むトムが田舎の祖父を、久しぶりに訪問したとしたらどうかな、とヒントを出します。」(88頁)
引用9.【「このコーヒー、さすがに薄すぎるやろ」】
「Is this tea or coffee? これも上の文と類似の疑問文です。「状況を想像し状況にふさわしい日本語を考えよ」と学生に言います。この場合も、例えば「薄いコーヒーであるのに不満なので、文句を言っている」と答えてくれる学生は少ないのです。柔軟な思考力、豊かな想像力が欠如しているようです。英文読解には、そんなもの使わないでいいと勘違いしているのでしょう。」(89頁)
引用10.【英文読解は慣習の想像を含むため想像力の涵養に役立つ】
「Mary struck John on the head. He had given a violent kick to her dog. これは前後関係を知らなくても理解できますから、すぐこれに相当する日本語文を書かせます。「メアリーがジョンの頭を殴った。彼は彼女の犬を乱暴に蹴飛ばした」。これで正しいでしょうか。had givenと過去完了形になっているのを無視したことから生じた誤りです。基本的な文法を知らない学生が増えています。正しい訳文は、例えば「メアリーがジョンの頭を殴った。彼女の犬を乱暴に蹴飛ばした彼に仕返ししたのだ」です。説明しましょう。過去完了は過去より以前のことをいうのですから、まずジョンがメアリーの犬を蹴飛ばした行為があり、その後に、彼女が復讐したのです。もう一点、学生が見逃しているのは、英語表現の慣習です。つまり、英語では何か意外な、驚くべき、予想外の発言をしたら、その説明をする義務があるのです。驚かせて放置するのは礼儀違反です。これは確立した習慣ですから、説明の冒頭に「というのは」という意味の接続詞forなどを付けないのが普通です。」(90頁)
上記の引用をあえて評者の私なりに整理し再構成してみよう。「引用7」で言われていることが重要である。実は、「和訳できなくても理解できていれば十分だ」と言いたくなるけれども、実際には多くの場合、和訳を通して初めて人は他の人にも伝えられる水準での理解を得ているし、それを他人が検証したり改善したりするのも和訳の微調整を通してなのである。明確な理解とは母語を使った理解であり、そのためには非母語と母語とを比べなければならず、そのためには非母語に対する想像力を働かせなければならない。「引用8」も「引用9」も「引用10」もそのことを言っており、読解し訳出する力とは、想像力の涵養を、論理上含まざるをえないのである。異文化理解がますます重要になる昨今、結局は「他者の靴を履いてみること(put oneself in someone’s shoes)」つまりは「他人の立場に立って考えてみること」が求められており、そのための練習場として読解訳出は適しているのである。さて、次節では、話題を変えて、この本から読み取れる英会話偏重主義の悲惨な帰結を見ていきたい。この本のタイトルが『英会話不要論』となっているのは、英会話をあまりにも(養育者が)重視した結果生じた実例を著者がたくさん目撃して、心を痛めたからであろう。この本を語る上で避けては通れない不気味な話題に、我々も赴くとしよう。
第三節:ペラペラ偏重の蹉跌
まず、「そもそも二つの言語を、抽象度の高低にかかわらず、母語レベルの練度で自由自在に使いこなし切り替える超人」というのがいるのかどうかを考えてみよう。著者の行方氏はこの問いに明確に「NO」と答えているように私には思われる。その根拠となる箇所を引用したい。
引用11.【バイリンガルも軸足をどちらかに置かざるを得ない】
「父親がイギリス人で母親が日本人の場合、子供はバイリンガルになるだろうと思う人がいますが、大まかな意味でならともかく、厳密な意味でのバイリンガルというのであれば、それは極めて難しいのです。特殊な条件でもない限り、どちらかが母語になり、もう一方は、いくら巧みに使えるとしても、外国語になるのが普通です。」(15頁)
引用12.【津田梅子ですら二言語の同時的熟達は難しかった】
「ここで、津田塾大学の創設者として知られる津田梅子の場合を考えてみましょう。彼女が一八七一年、岩倉使節団とともに渡米したのは、満六歳のときで、すぐに愛情深いアメリカ人夫妻に引き取られ、現地の小学校に通いました。英語はまったく知らなかったのですが、じきに覚えたようです。適応性、積極性に富む利発な少女だったのでしょう。英語だけに囲まれた環境ですから、まさに「アメリカの赤ちゃんが覚える」のに近い状況で、話せるようになったのでしょう。現地の小学校、女学校をよい成績で卒業し、十七歳で日本に帰り英語を教える仕事に従事し、数年後に再度渡米し、一流女子大のブリンマー・カレッジを卒業。日本に戻り、津田塾創設など女子教育に多大の貢献をしました。ところで、彼女にとって大きな問題は日本語でした。長い間使用しなかったので、帰国後は母親とのコミュニケーションのために、通訳を介さねばなりませんでした。本人は六歳の時知っていた日本語を思い出しながら、話せるようにとずいぶん努力したのですが、ついに果たせなかったようです。残された書簡はほとんどすべて英語で書かれています。」(16-17頁)
引用13.【完全なるバイリンガルなど存在しない】
「友人の教え子で国立大の英文科を最優秀で卒業した女性の話を聞きました。人も羨むような国際結婚をして、今はアメリカで夫と男女二人の大学生の子供と暮らしています。昨年一時帰国して、友人に会った時、家庭で孤独な瞬間があるとこぼしたそうです。夫と子供が夢中になって話し出すと、彼女はついて行けなくなるそうです。1番困るのは、英語が聞き取れなくなることだそうです。二◯年近くアメリカ人の夫と暮らしてきた人が、未だにリスニングが完璧でないというのには、驚きませんか?[…]正真正銘のバイリンガルなど、なかなか存在しないというのが、この女性の例でも分かりますね。」(17-18頁)
私は大学時代にフランスへと交換留学をしていたことがあるのだが、いまフランス人と話すのは、とてもゆっくりとしかできない。そのことが悔しいので、妻とフランス語が使える駒込のバーに行こうとずっと前から決意している。決意しているのだが、妻のほうが先にバーに行ってしまった。私は未だに足踏みしている。そもそもバーで話せるような小洒落た話題が私にはないし、バーで話すようなスピードについて行こうとすると疲れてしまうだろう。私はあのバーに、行けない。要するに、私も日本語に軸足を置かざるをえないのである。
では、こんな口下手な私でも、幼少期から外国語にどっぷりと浸かっていれば、ペラペラになれたのだろうか。この本を読む限り、なれたのかもしれない。しかし、そのことがどのような帰結を生んでいるのかを注視してみるのが、本節の主眼であった。以下の記述を引用してみたい。
引用14.【母語の第二段階に到達する機会を放棄してまで外国語の第一段階に到達したいのか】
「この問題について参考になる良書があるので、勧めました。市川力氏の『英語を子どもに教えるな』(中公新書ラクレ、二〇〇四年)です。著者はシカゴの塾で十数年にわたり国語を教え、海外駐在員の子どもの相談相手を務めた方です。教え子は一〇〇〇人にも及ぶそうです。帰国子女の英語学習について、これほど、豊富な実例を上げて、問題点を的確に論じた本はないので、そこに上げられた実例をいくつか紹介させて頂きます。市川氏は、本の題名からお分かりのように、帰国子女の英語学習に否定的です。海外派遣が決まった両親が、この機会に子供が英語がペラペラになるだろうと、過度の期待を寄せた結果、子供が日本語も英語もいい加減な、気の毒な人間になった実例を余りにも多く見たからです。「英語環境の中にどっぷりつかることで、ネイティブ並みの発音で日常会話はできるようになっても、なかなか十分な読み書き能力は身につかない、母語である日本語の力を育てるのが難しい、母語喪失のリスクを負ってまで獲得した英会話の力も日本に帰国して使う機会がなければみるみるうちに失われていく、といった事例に数多く接してきた」と「はじめに」にあります。そもそも、日本語でも英語でも、子供は成長過程で、まず簡単な日常会話ができる「第一段階」を経て、次に、学校で理解、社会、数学、国語などの教科を理解できる「第二段階」へと進んで行きます。市川氏に依りますと、小学一年生から中学一年生くらいまでの日本の子供、つまり日本語で「第一段階」に達した子供は、英米で暮らして英語に囲まれていると比較的早く、英語でも「第一段階」に達します。しかし、日本語の「第二段階」に達するための努力を怠っていると、いくら現地で暮らし、友達と自由に喋っていても、英語の「第二段階」に達しないのです。」(31-32頁)
引用15.【娘を拒食症にしてまで娘を英語ペラペラにしたいのか】
「C子さんが市川氏の塾に入った時、現地校の中学二年生でした。生真面目な性質で、完璧主義だったので、学校での作業や宿題をきちんとこなせない自分を許せず、結果として不登校気味になりました。彼女は英語の「第一段階」には達しても「第二段階」にはかろうじて届いたというだけだったのです。[…]とうとう拒食症になりました。相談した医師は、日本人学校への転校、あるいは日本への即時帰国を強く勧めました。ところが両親はその勧めを無視して、現地校に通わせ続けました。というのは、日本の帰国子女枠で高校入試を有利に受けさせるためには、あと半年現地校に在籍する必要があったからでした。帰国子女枠というのは、受験勉強が充分出来なかった帰国子女も、英語力など一般の受験生にない長所があるので、通常の入試とは違う、学科の面ではより易しい問題を課す特別の枠のことです。数年前から日本の中学、高校、大学で設けられている制度です。高校入試の場合、現地校での在籍が二年以上であることが条件になっています。さて、C子さんは、病気が治癒せぬまま、現地校に留まり、帰国後、この枠を用いて、志望の高校に合格できました。しかし、不幸なことに、拒食症はついぞ治りませんでした。」(35-36頁)
引用16.【小学校で英語教育をしてもしなくてもどうせ第二段階には進めない】
「「あの子は帰国子女だから英語に強い」と言われるように、「あの子は小学校で英語をやっていたから英語に強い」という話を聞いたことはないでしょう?事実、そういう子は滅多にいないからです。中学で初めて英語を学び出した大多数の子供より、優位を保てる期間はせいぜい半年で、後は同じになります。どうして文科省は、こういう調査結果を考慮しないのか不思議です。」(47頁)
引用17.【徹底して損得で考えるなら小学校で英語を教えないほうがよい】
「結論として、どう考えても、小学校への英語導入の損得勘定はマイナスではないかと恐れます。膨大な予算の使い方についても、税を負担する国民としては文科省に強く再考を促したいものです。」(49頁)
「引用14」と「引用15」を読んで私は驚いた。そんな事例が多数あるのかと驚いた。養育者が過度のプレッシャーを与え、子の自然な成長順序を歪めてしまう場合があるのだ。子の方は、やりたくもないことをやらされ、「社会は、制度は、こうなっているんだから、これで良いんだ、諦めろ」という言説に晒される。神経衰弱になっても不思議ではない。結局のところ、英語に「どっぷり浸かる」のではなく、まずは日本語を勉強し、日本語を用いて、英語を文法的に分析するという順序の方がよほど着実そうであるという、穏当な結論が出てくるのであった。では、やや唐突だが、力士はどうなのか。力士は文法なしで日本語を理解しているのではないか。行方氏はこの疑問にさえ答えようとしている。引用しておこう。
引用18.【力士が文法学習なしで日本語を話せるのは日本語文法学習よりも壮絶な努力をしているから】
「力士は親方のもとで、同門の力士たちと朝から晩まで、常に一緒に行動します。入門当初は、個室などあるかどうか。相撲の世界では、プライバシイという考えはありません。故郷には、家族、時に親類まで、彼からの仕送りを待っています。日本での生活が耐えきれずに、帰国することは、事実上、不可能です。相撲技術の獲得には、親方や先輩、仲間との間で日本語を使わねばなりません。言うまでもなく、相撲の厳しい訓練、私生活のなさ、日本語の難しさ、などに負けて、挫折する力士もいます。肉体的な強靭さに加えて、精神力、忍耐力、家族愛など、あらゆる面で優れていて、初めて、僅かな歳月で役に立つ日本語話者になれるのです。外国語である日本語を上手に喋っているところだけ見て、羨ましがっても無意味です。生活の全て、我慢強さ、などを真似られぬ限り、力士が「文法など知らなくても結構喋っている。自分もあのようにして英会話を身に付けたい」と望む人が仮にいたら、相撲の激しい朝稽古を見学させてもらうのがよいでしょう。」(140-141頁)
第四節:書評の終わりに
本稿では、行方昭夫著『英会話不要論』に沿って、「読み書き偏重」の有用性と、やたらペラペラになろうとすることや、誰かをペラペラにしようとすることの問題点について検討してきた。どうやらこうした問題関心は著者ひとりのものではなく、英語教育研究者のあいだで共有されはじめているようだ。以下の引用を最後に提示したい。
引用19.【対ペラペラ戦線】
「教え子で、東大での同僚でもあった、斎藤兆史氏の『英語達人列伝』『日本人と英語』などいくつもの著書からも、大きな刺激を受けました。以前、同君から、ペラペラ喋ることのみ大事にする英語教育への批判で、「共闘しましょう」という誘いを受けたことがあります。最初は冗談半分に取っていましたが、本気でそうしなければ、という気持になりました。」(183頁)
引用20.【文法を軽視する風潮への警戒】
「世間一般の方々が英語学習に関心が深いのは結構ですが、あまりにも多くの勘違い、誤解があります。なんの悪気もなく堂々と「文法なんかやっているから喋れるようにならないのでしょ」と発言する、ごく普通の親御さんが大勢います。これらを是正したいという気持が自分の中で次第に高まって行きました。」(184頁)
いま、これを書いているのは日曜である。私は来週も、この書評の冒頭に書いたような授業を実践していくのだろう。そのとき、読み書き、文法を学ぶことの意味、魅力を同時に伝えていきたい。私は、そもそも、あなたにペラペラだと思われたいのではなく、あなたの言っていることをきちんと理解したいのではなかったか。日本語だろうと、英語だろうと、フランス語だろうと、そのことだけは動かない。この本は、この一番重要な一点を、私に想い出させてくれる本であった。
石井 恭平
『人生に期待するな』(北野武著、扶桑社、2024年)
評者:石井 恭平(ヴェリタス英語科講師)
第一節:この本と私との出会いについて
あれは9月のことであった。高校時代から、私がその縦横無尽の活躍に圧倒されるしかなかった、さる高名な人物が、ネット上の誹謗中傷や有力者たちの政治的思惑にひどく翻弄され、自殺した。生前、かの女は時めいていたのである。この社会の周縁に常に身を置いてきたし、しかも全然そこから出る気がない私のような人間から見たら、このかたは、高校の同期の中で1番、輝いてみえていた。私はかの女の死のことを聞き、高校時代、物理学の実験でこのかたとペアになると、このひとにほとんどの作業を代行してもらっていたことを即座に想いだした。私が当時、物理学の授業を聞いていな過ぎて、実験で使いものにならなかったからである。そしてあのときの感謝の念と、反省の念が込み上げた。おそらくかの女は、私のことなど覚えているはずもなかったが、私は覚えていた。
そして、いつも以上にふさぎこみ、その後しばらく放心していた私だったが、ふと、自分があるドラマを、すがるように、見ていることに気がついた。『ツイン・ピークス』というドラマである。高校で一番の美少女であるローラさんがある日、なぜか、河原で突然、変死体で見つかる。その原因を村のみんなで考えてみると、だんだん人間の最奥部に眠る、闇と優しさとが、対をなしながら怪奇現象とともに噴き出してくるという、錯乱した内容のドラマである。誰が犯人か、なんてことはどうでもよくて、少女の死によって人々の心が根底から揺さぶられ、普段考えることが難しかったことをみんなが直視するようになる。そのことが重要なのである。数話ぶんみていたら、私もだんだんそのドラマの中の登場人物たちと同じように錯乱してきて、本駒込の本屋にふらりと入っていった。今思えば、私は何かしら、人間のくすしき最奥の光と闇とを抉り出すような言葉を、求めていたのだと思う。そんなおりに出会ったのがこの本『人生に期待するな』(北野武著、扶桑社、2024年)であった。
私はこの手の本を買うタイプの人間では全然ないから、最初は立ち読みだけで全てを読んでしまおうとした。数時間もあれば読めそうな文量しかなかったのだ。この本は2024年に出た本だから、買うと税込で1650円もするのだが、私は、1650円で新品の本を買うことは絶対にないと言い切れる。私は貧乏人なので、中古本しか買わない。さらに、なぜ私が新品本を決して買わないだけにとどまらず、この手の本を一切買わないのかというと、私には、芸能界の伝説的人物の語りを読みこなす能力が欠けていると思われるからである。
著者の北野武氏について、もちろん通りいっぺんのことは知っていた。しかし、私は芸能記者ではないから、有名な「フライデー襲撃事件」についての歴史的評価さえも正当にはできない。この事件の原因も真相も、詳しく知らないからである。また、私は映画が大好きなので近作『アウトレイジ(2010)』も『浅草キッド(2021)』も『首(2023)』も見ているけれども、死と隣接しながら撮っているかのような、あまりに美しい前半期の映画群、たとえば『ソナチネ(1993)』について正当に評価できるほどの能力が私に本当にあるのかというと、おそらくそれも疑わしい。北野氏の映像は、私ごときが語るには、美し過ぎる。そう思って生きてきた。
しかし、立ち読みしていて即座に気づいたのは、この本が私のような人間が読んでも、無類に面白いということであった。よく読むと、圧縮された堅実な思索の跡が見えてくるからである。ややもすると「飛躍がある」「不整合がある」「無骨である」などと批判されかねない短文の連続に、私はだんだんハマって行ってしまった。だから私は、この書評を依頼されたとき、私が普段読んでいることが多い映画本でも哲学書でも語学書でもなく、あえてこの不思議な書物を紹介してみることにした。北野氏の、韜晦しているような筆致にときたま当惑を覚えつつ、行間を埋めるように読んでいく読書も、読書の愉悦の一側面を確実に捉えるものであると私は思ったのである。自分なりに整理して読んでいく、余白に自分の体験や反論を書き込み、共感や違和感といった、自らの情緒の揺れを味わう。芸能界の伝説的人物の文章を、自分の普段の思索内容との距離を測りながら、慎重に読んでいく。そういう体験を、私は読書に求めてもいいことが分かった。新鮮だったのである。こうしてこの本を買い、家に帰ってすぐに読み終わった。
この本の中には、かの女の死を受けて私が友達にモゴモゴと呻吟していたような言葉とよく似た言葉が冒頭から書かれていた。まずはそこから紹介しよう。以下、引用は、ひとつを除いて、すべて同書から引用していく。紙幅の都合で改行を省略した箇所があることと、強調のための太字は私によるものであることとを、あらかじめ断っておく。また、【隅付き括弧】の中は私が引用を要約したものである。
引用1.【SNSこそが残酷なのだ】
「ネットのSNSってのは残酷なもんだ。リアルの世界では何もできないような匿名の連中が、鬱々とした気分をSNSで誰かにぶつける。不平不満や嫉妬なんかのネガティブな感情を、たまたま見つけたターゲットに向かって吐き出してるわけだ。」(21頁)
引用2.【SNSというニワトリ小屋に自分から入っていくのは自発的隷従に他ならない】
「芸能人やスポーツ選手なんかも、わざわざ自分が叩かれてるSNSをのぞきにいかなきゃいいのに、そこへ入った途端、もう抜けられなくなって袋だたきにあって、精神的に追い詰められたりする。ああいうのは、ニワトリ同士がクチバシでつつき合ってるニワトリ小屋に自分から入ってくようなもんだ。もうそろそろ、こんな不毛なやりとりをするための薄っぺらいスマホなんかとは手を切る時期にきてるんじゃないか。スマホなんか捨てちまって自由にならないと、みんなどんどんおかしな世界に入り込んじまう。あんなものに依存しているから、毎月、お布施のようにチャリンチャリンと金をむしり取られ、自分の頭じゃ何も考えられなくなって、しまいには精神が不安定になる。スマホ依存、ネット依存なんてのは、奴隷の手鎖と一緒で、これは自分から好きこのんで奴隷になってるようなもんなんだ。」(23頁)
私は、(芸能人の方とお話をしたことは、なぜか相当量ある部類の人間だと思うので)、私の生が芸能人の方々のそれとは、どれほど異なるのか、もっとはっきりいえば、無縁かを心得ているつもりである。しかし、この本は表紙にも、「全ての悩める現代人に捧げる、たけしによる福音書。」と書いてある通り、この世界の仕組みやその中でのヒト一般の生き方を平易な言葉で論じたものでもあるわけだから、私にもその部分については書評が書けるように作られているのではないかと思われた。実際、福音書はイエスの人生について詳しく知らない人にも分かる、ある倫理の深層をえぐり出しているからこそ、日々新たな読者を獲得しているのではないのか。なるほど、この本は、バイク事故やフランス座などにおける個別的経験から題材を取ってはいるが、その分析から普遍的意義を引き出すところにまで思索を練り上げていくことに成功しているのではないか、と私には思えた。
引用3.【体験の強度を創作活動に取り入れる】
「オイラ、本物のヤクザが殺されるところを見たことがあったから、映画でもそうしたシーンを取り入れたりした。それは、全く違う世界からの啓示みたいなものじゃなくて、全ては自分の経験からなんだよ。」(152頁)
だから、仮に「引用3」のような言葉を見つけても、それほど読者諸氏とは無縁の話だと思う必要はない。著者は、強烈な具体的体験から出発しつつ、その体験を前提せずとも理解できる構造をそこから取り出していく優れた書き手だからである。以下では、テーマごとに各節を分け、私にとって興味深く思われた箇所を順に評していく。
第二節:金儲け主義の浸透がもたらす荒廃について
まず、現代社会の金儲け主義について北野氏が優れた分析をした箇所を取り上げてみよう。少し長いが、以下の引用を読んでみてほしい。
引用4.【ディヴァイド・アンド・ルール】
「世界的に経済格差が広がって、オイラ発展途上国の人の知り合いもたくさんいるけれど、そうした国の中にも税金を懐に入れちゃうような連中がいるよね。そんな世の中で金持ちが考え出したやり方っていうのは、「無限大の思想」なんだよ。どういうことかっていうと、例えば1メートルを半分の50センチ、さらに25センチっていうように、どんどん細分化していけば無限に1メートルを分けられる。同じように、貧乏な人の中にも細かい格差、序列をどんどん設けていけば、その中で貧乏同士がひがみ合い、やっかみ合い、足の引っ張り合いをするだろうってやり方なんだね。貧乏な人の敵意は、本来なら金持ちの人に向かうべきなんだけど、こうした格差や序列の中で貧乏同士が敵視し合うんだ。「自分は、下のヤツよりもちょっとだけ上」っていう意識を植えつけることによって、常に自分より下がいる。そうやって線引きをすればいくらでも貧乏な人たちを細分化していけるし、貧乏同士、いがみ合ってくれるというわけだ。そうやってうまくガス抜きをやっていけば、金持ちに敵意が向かなくなる。こういうのは、大衆をコントロールする一つのやり方なんだな。」(58-59頁)
引用5.【環境問題が解決しないのはその方が儲かる仕組みが整備されているせいだ】
「省エネやリサイクルなんかが大切なことは、頭では十分わかってるはずなのにできない。どうしてできないのかっていえば、経済のシステムを大量生産大量消費から変えられずに無駄遣いを勧め、環境汚染を垂れ流すほうがコストが安くて利益になるって具合になっているからだ。じゃんじゃん買い物をし、食い物は残ったら捨て、プラスチックを使い捨てる。こんなふうに地球規模でどんどん消費活動をしてもらわなければ、グローバル企業がもうからないようにできてるんだ。」(53頁)
引用6.【幸福度を金額でしか表現できないと思い込ませるのが資本主義のシステム】
「今の資本主義経済万能の考え方だと、結局はどんだけ金を持ってるかで幸福度を測るしかない。そんなのは一面的な価値観で、幸せなんてのは100人いれば100通りあるんだよ。金持ちが全てを持ってるわけじゃないし、金持ちが持ってないもんを貧乏な人が持ってたりする。」(190頁)
鋭い観察に、既にして唸らされる読者諸氏も多いだろう。私もそのひとりであった。「引用4」において、無限分割可能性は社会階級にも見出され、その心理的効果が鮮やかに記述されている。「引用5」でも、環境問題の帰責は個人の心理にではなく構造にこそ向けられるべきだとの指摘がある。どちらも大変興味深い箇所であるが、あえて私がここで詳しい分析を試みたいのは、「引用6」である。現行資本主義の社会には、ある重大な人間に対する単純化がある、と私は以前から考え続けてきた。その単純化をこの「引用6」は見事に射抜いている。
まず私の立論の前提を明らかにしておく。人間は、快楽ではなく意味を求める不思議な生き物である。意味さえあれば不快さえ欲するのが人間である。「断食」は苦痛であるが、神の教えに適うと意味づけられればやりたくなる人もいるのかもしれない。「切腹」は苦痛であるが、名誉ある行為としてみなされていればやりたくなる人もいたのかもしれない。タバコは咳を、コーヒーは苦味を肉体にもたらすが、憧れの先輩のようになれるならやりたくなるかもしれない。人間は事実として、そうやって生きている。人間は「快苦の原理」では到底可能にならないはずの事柄を「意味の原理」によって、平然とやってのける。動物ならば大喜びで飛びつくビーフジャーキーが目の前にあっても、それの所有権が他人にあると知れば人は遠慮するだろう。京都に行って、美味しそうなぶぶ漬けが目の前に供され、「是非食べてください」と言われても、その意味を考え過ぎる人ならば、家に帰るかもしれない。マリーゴールドを貰って、あいみょんを想起するならいいが、花言葉を想起するなら怖くなるかもしれない。人は、花をもらったときにその意味を考えずにはいられないのである。韓国のボーイズグループRIIZE(=ライズ)のメンバーであるスンハンさんが不祥事を起こした後、大量の葬式用の花が事務所に贈られたそうであるが、贈られた側は、これがどのような意味かを考えないわけにはいかないだろう。このように、何事にも意味を経由してから触れてしまう人間観の提示を私がしたところまでは、これ以上の証明はせずに、前提させてほしい。人間とは、快苦をかなぐり捨ててでも、意味のほうを気にする特殊な動物なのである。
さて、ここからが、現代社会に見られる、こうした人間に対するある重大な単純化を指摘する段である。北野氏が「引用6」で述べる通り、人間が求めている意味を、現代社会は「換金」というやり方でしか人に認識させまいとしているのだ。これが問題中の問題なのである。どういうことだろうか。
たとえば、こういうことが若者の間でささやかれているのを、私は聞いたことがある。「初任給をもらって本当に嬉しかった。なぜなら、収入があるってことは、私が社会から求められているっていう、証拠だから」と。しかしこの発言について、ちょっと考えてみてほしい。この発言、裏を返せば、収入がないと、「証拠(=エビデンス)」がないので、自分には生きる意味がないことになりかねない、そういう構造の中で生きている、ということを言っているようにも受け取りうるのだ。この発言に対して、普通は「初任給、貰えてよかったね」と、人々は口々に言うのだろうが、私には「よかった」と言っていいのかどうかが正直わからなかった。
大金持ちになれば、自分は世界で求められている有意義な人なのだと分かり、貧乏になれば、自分はこの社会において無意味なのだとわかる。これはたしかに分かりやすいシステムではある。だから、前提としてあらかじめ述べておいたように、意味を求める動物であるところの人間は、このシステムを嬉々として採用してきた。現代において、「意味」が欲しければ「金」を稼げばいいのだ。「世界に求められている」とか「自分には自己効力がある」とか、そんなふうに思いたければ、「金」を稼げばいいのだ。
しかし、ここで立ち止まって考えてみたい。人間にお金は必要である。お金は嬉しい。しかし、人間はそんなに金持ちになりたいのだろうか、と。「人間が本当に欲しいのは意味ではなかったのか?」という問いを私は立てざるを得ない。
たとえば、詩作を例にとって説明してみよう。たしかに、誰にも読ませない詩をひとりで書き続けて、それでも豊かな意味世界を生きれるから大満足だという人はかなり少ないだろう(とはいえ、エミリー・ディキンソンという詩人は、生前ほとんど無名であり、40冊の詩作ノートは死後に親族に見つかって出版され、そのあとで大詩人として有名になったわけだから、そういう詩人もいるにはいるわけだけれども、こういう事例は少数派であることは、やはり動かない)。では、人間は満足するためにその詩を換金したいだろうか、とさらに問うてみて欲しい。「不要」とは言わないにしても、「必然的」とまでは言えないはずだ。かくいう私も人に贈るための詩を書いたことがあるのだが、同居人に夕食のときに聞いてもらったり、誰かに批評してもらうだとかすれば、かなりの満足感を得られた。その体験は、とても有意義であった。あるいは、友達を集めて詩の朗読会をしたら、さらに楽しかっただろう。話を戻そう。私が言い
たいのは、「意味が欲しいのはわかるが、そんなにその詩を「換金」したいだろうか?」ということである。何度も言うが、たかだか100年弱の生の中で、人間がひたすら求めているのは「意味」である。意味がちゃんと濃厚な体験を通して感受されるならば、「カネ」という分かりやすい指標が与えられることは、実はそこまで重要ではないのではないか。このように、丁寧に日常を分析してみれば、意味とカネの結びつきが実は必然的ではなく、じつは恣意的であるのにもかかわらず、さも必然的であるかのように偽装するところに、現行資本主義の最大の詐術があると私は指摘する。
さらにもっと踏み込んでみたい。「その詩を換金することで本当に意味づけはより濃厚になるのだろうか」と私は問いたい。たしかに、質が量に転化されることで、より「分かりやすく」はなるだろう。たとえば私の書いた前述の詩が一個10円で売れて、印税が入れば、どれくらい私の詩が社会にとって有意味なのかは多少「分かりやすく」なる。それは認める。しかし、「分かりやすく」はなるけれども、人は前提しておいた通り、意味を求める特殊な動物なのであるから、人はその印税をもらうより、直接その詩について、誰かとコミュニケーションが取りたくなるのではないだろうか、と私は予想する。要するに、人は「カネなんかじゃ満足できない」はずなのである。「カネなんかいらねえよ!」と吐き捨てる詩人さえいるかもしれない。実はあらゆる生産物一般にこの詩作事例と一脈通じるものが、本当はあるのである。よほどのブルシットジョブをやらされているのでなければ、「仕事」はカネでその意味が表示されるよ
りも前から、その場その場で刻々と現れて、味わわれていくような、コンサマトリーな、そのたびごとの新しい意味に満ちている。というか、だからこそ、やれるのである。つまり、どんな仕事も、結果に至る前の過程が、そこそこの価値を既に持っているはずなのである。北野氏も、結果として得られる収入ではなく過程が既に分泌する価値に注意を喚起する。
引用7.【カネをもらうためにやっていると捉えない働き方もある】
「泳いでいる魚に「お前、偉いな」って褒めるやつはいないってことで言えば、働くってことに関してもオイラの場合は、魚が泳いでいるように何かを作ったりするのであって、別に働いてるわけじゃない。映画を撮ることにしても小説を書くことにしても絵を描くことにしても、単にそれをやってるだけで、それを働くこと、労働としてとらえたことはないんだよね。」(79頁-80頁)
もちろん、「過程において意味さえ与えられれば、結果においてカネは要らないよね」などという逆方向の人間に対する単純化を私はここでするつもりは全くない。私は「やりがい搾取」に繋がる論理を決して肯定はしない。そうではなくて、生活の中に満ち満ちている様々な意味は、カネでしか表現できないわけではないし、量的に表現した瞬間に、不可逆的に劣化変質してしまうものだというこの一点を、私は確認しているのみである。
あるニュースで、「世界の超富裕層26人、世界人口の半分の総資産と同額の富を独占」という見出しがあった。古いニュースだから、今この数字は「26」ではないだろう。とはいえ、なぜ、こんなにも、富裕層はやたらとカネを欲しがるのだろうか。その答えは、先ほど前提した人間観からすぐに導出できる。富裕層も人であるから意味が欲しいのだが、その意味を確認する方法が、カネをたくさん持つという間接的方法しかなくなっているからである。つまり、富裕層として世間の槍玉に挙げられかねない、この26人の性格がガメツイから、こんなにたくさんの富を彼らが独占しているわけではない、と私は考えている。むしろ、彼らは、現行システムによって、意味を確認する手段が口座の数字を見るという間接的方法以外にはないと確信させられてしまっているだけではないのか。しかし、いくら数字を見ていても直接的にはやっぱり満たされないから、もっともっと質を間接的に表示できるとされるカネの量を増やそうとする。こうしてカネを増やす様々なサブシステムを作り、その運営が滞りなく進んでいるかどうかをチェックする会議で忙しくなる。忙しくなると、尚更、目の前の生活の中に満ち満ちる意味を感受する時間がなくなる。彼らは、足元以外を常に探すが、探しているものは常に足元に
あるのである。私は現行経済システムの最上層にいる彼ら26人こそ、このシステムの最大の犠牲者であるという見方すら可能だと言っているのである。彼らは足元にある意味の、直接的感受の機会を奪われ、生きる意味を表示することになっている間接的記号を探すよう、迂遠な経路へと常に駆り立てられているのだから。だから彼らは決して止まることがない。意味を探して、休むことなく勤勉(=インダストリアス)に走り続け、システムを回すのである。北野氏もこのシステムに対する警戒を促している。
引用8.【ネットはマッチポンプの金儲けシステム】
「ネットを利用したり、自分たちに都合のいいシステムを作って金儲けしてるような連中はしたたかだ。夢をなくした人に対してフォローしているような上手さもある。これはマッチポンプで稼ぐようなもんで、麻薬の売人が麻薬更生施設を経営してるのと同じなんだよ。だから、どう動いたって金を取られちゃうという仕組みになってる。」(25-26頁)
引用9.【カネをむしりとるシステムに過ぎない「マッチングアプリ」】
「マッチングアプリっていやあ何でも通ると思ってるんだけど、その実態はマルチ商法の引っかけサイトだったり、売春斡旋とかパパ活専用サイトだったりするわけで、マッチングアプリと言い換えてるにすぎないわけだ。」(24-25頁)
では、どうすればいいのか。今ここにある足元の濃厚な意味を感受すればいいのである。「引用6」で「金持ちが全てを持ってるわけじゃないし、金持ちが持ってないもんを貧乏な人が持ってたりする。」と北野氏は注意深く言っていた。そう、富裕層がマネーゲームに心をすり減らされて不満足になるとき、貧困層は今ここにある一杯の水を味わう術を知っており、満足するだろう。目の前に充足があるのに、遠くの記号を追う迂遠なマネーゲームに参加するのは勿体ない。以下の「引用10」は、カネというより意味を求める特殊な動物である人間の実情を捉えている。
引用10.【カネ儲けのために今ここの意味的充足を犠牲にするのは本末転倒】
「そもそも夢を抱けとか成功しろとか金持ちになれなんて尻を叩く連中が、なんでそんなことを言うのかと考えてみれば、夢を抱いたり金持ちになろうとあがいたりするような人間がたくさんいないと経済が回らないからなんじゃないだろうか。そんな連中のために、大事な今の時間を使うなんてのはバカなことだと思う。だって、どんなに金持ちになって高いワインを飲んだとしても、喉が渇いたときに飲む一杯の冷たい水のほうがうまい。どんな高級レストランの料理でも、母ちゃんが握ってくれたにぎり飯に勝るものはない。贅沢すれば幸せになれるわけじゃない。いくら貧乏でも心構えひとつで人生の大切な喜びはすべて味わえるもんだ。オイラ、演芸場で漫才をやり始めたころ、一日、終わっても金になんねえし、これから売れるかどうかもわからなかったんだけど、とりあえず一生懸命、舞台に立って客にも受けたからいいかって思ってた。」(103頁-104頁)
私はここを読んだ時、先日ある大学のゼミが終わったあと、そのゼミの教授に連れて行ってもらった宴会で、教授が言った「ひとりの師匠、ひとつの本、ひとりの友、それだけで人生は楽しくやっていける」という言葉を直ちに思い出した。『徒然草』の第123段で、卜部兼好は、人生に必要なものは、「食物、衣服、住居、医療」の4つだけであり、この4つ以外を求めるのは「奢り」であるとまで述べている。これは「物的な知足」を説く言説であり、現代でも一定の説得力があるだろう。しかし、北野氏や先ほど引用した教授の言葉は、卜部の言葉とは異なり、「意味的な知足」をも説く言説である。意味的な知足とは、カネによって表示される意味で間接的な満足にだまされる、つまり事実上の不満足に陥るのではなく、目の前の日常からカネに還元される以前の豊かな意味を汲み出すことである。人は物質的に知足するのみならず、意味的にも知足せねば、幸福にはなれまい。私はそのことを、この本から再確認させられた。
第三節:機械の限界について
この本で北野氏は、近年その可能性ばかりが強調されている「AI」というもの、いやそもそも「機械」というものの、限界の方こそを厳しく見つめている。それは機械を作っている人間についての、現代的で、正確な理解から可能になるものだと私は考えている。人間と機械との関係を論じた、以下の引用を取り上げよう。長い引用になるが、この箇所は本当に分かりやすく書かれているため、すらすらと読めてしまうはずである。
引用11.【人工知能には感情が再現できていない】
「人工知能、AIなんていうけど、人間の脳をデジタルで再現するのは今のところかなり難しいね。AIの技術が発達しても感情まで再現できるのか、オイラは限りなく疑問に思うんだ。もちろん、AIってのは人間の脳の代替じゃないんだけど、チューリングテストなんてのがあるように、AIの当面の目的は、人間が「人とコンピュータの区別」をつけられなくなることだ。そういう意味なら、AIもかなり人間をだませるようになってきてるんだけど、人間の脳を再現するまでにはなってない。人間は自分たちの脳のことなんて、まだほとんどわかってないんだから当たり前だ。」(38-39頁)
引用12.【脳のシミュレートは神レベルにならねば不可能】
「人間の脳とAIってのは、構造やシステムが根本的に違うんだね。人間の感情っていうのは、指先がちょっと痒いだけで気分が変わったりするくらい微妙なもんだ。指先がちょっと何かに触れただけで、パッと新しい考えが頭に浮かんだりするのが人間の脳なんだから、それは人工的にそっくり精緻に再現できるなんてもんじゃない。せいぜい、指先が触れた物質が柔らかいものなのか硬いものなのか、卵かガラスか程度を判断できるだけで、人間の持っている感覚をシミュレーションでなぞらえることは少なくとも今の技術じゃできないんじゃないかって思うね。それができたときにおそらく神の存在、神ってのがどん
なものかがわかるんじゃないか。それくらい、期待されている人工知能の技術ってのはすごいことなんだけど、今のAIやChatGPTなんかがそのレベルに到達できているわけじゃない。人間の脳ってのは、宇宙や深海よりもずっとわけのわわからない世界だ。自分のことを自分で理解できないってのは一種のパラドックスだと思うけど、喜怒哀楽なんかの原始的な情動反応から始まって、高度な思考の仕組みやヒラメキみたいなシナプスの結びつき、複雑な記憶の回路なんかの脳の機能を人間が理解するのはかなり先、もっと言うと永遠に不可能なんじゃないかってオイラは思ってる。」 (39-41頁)
引用13.【人間は既成の仕組みを利用したり消費しているだけでアリ一匹さえ創れていない】
「量子コンピュータが実用化されたとしても、人間の本性は変わらないんだから大きな変化はないだろう。だって、動物でも植物でもなんでも実際、生命自体を人間が創造したことはまだないんだよね。DNAについてわかったとしても、人工的な光合成に成功したわけでもないしね。例えば、我々がいつも食べている米だけど、炭素や水素、窒素なんかの原子や分子の構成はわかったとしても、米を人工的に作り出すことができているわけじゃない。植物は、光合成によって水を分解して酸素を作り出して二酸化炭素をデンプンなんかの有機物にするわけなんだけど、人間は自分でそんなふうに食料を作ったこともないんだよ。人間はそうした仕組みの分析はできるし、植物を利用して農業をすることはできるんだけど、そうした仕組みを作り出したことはない。石油や天然ガスなんかの化石燃料にしても、それを掘り出してただ単に使っているだけで、自分で化石燃料に匹敵するようなエネルギーを作り出してはいない。何ひとつとして人間は新しいものを作り出しちゃいないんだ。人間の科学技術は進歩しているように見えるけど、実際には自然が作り出したり何億年もかけてためてきた資源をただ消費しているだけなんだ。その結果、地球のバランスが壊れて、世界中で異常気象が起きている。」(43-44頁)
「引用11」において北野氏は、機械と人間とが、ときに混同されることはあっても、なお同一とは決して言いえない理由は、機械に人間の「感情」をシミュレートできないからだと述べている。では、人間の感情をシミュレートするためにはどうしたらいいかと言うと、脳をシミュレートできればいい。しかし、人間は脳なるものをシミュレートできているのかというと、そもそも脳で何が起きているかすら、詳しく分かっていないのだから、できているわけがない。脳はあまりにも複雑な機構を持っているのである。では、人間の脳が無理なら、アリくらいならできているのだろうか。実は、アリもできていない。アリの代わりになれるようなアリロボットはない。では、アリの細胞一個くらいならばできているのだろうか。私は分子生物学に明るくないが、どうやら「細胞膜」を人工的に作ることこそが難しいのだが研究中、というような段階らしい。ことほど左様に、「引用11」から「引用13」では、機械が決して人間の代替に、完全にはなり得ないということが理路整然と書かれている。「引用12」において、脳と心の間の関係を決める法則を知ることは、神の叡智にあずかることに等しいと北野氏が喝破する点で、フランスの神父ニコラ・ド・マルブランシュの認識論を想起する読者もいるかもしれない。私は、ここの記述を読んで、小林秀雄が1959年の『文藝春秋』に掲載した「常識」についての文章を想起させられた。それは次のような文章である。
引用14.【常識は機械の限界を既に人に告げている】
「先日も、漫然と教育テレビを眺めていたら、ある先生が、現代生活と電気について講義をしていたが、モートル(Motor)が、筋肉の驚くべき延長をもたらしたが如く、エレクトロニクス(electronics)は、神経の考えられぬ程の拡大をもたらした、と黒板に書いて説明していた。一般人に向っての講義では、そう比喩的に言ってみるのも仕方がないとしても、そういう言い方の影響するところは、大変大きいのではないかと思った。例えば、人間の頭脳に、何百億の細胞があろうが、驚くに当らない。「人工頭脳」の細胞の数は、理論上いくらでも殖やす事が出来る。ただ、そう無闇に多くのデータを「人工頭脳」に記憶させるには、機構を無闇に大きくしなければならず、そんなに金のかかる機械では実用に向かないだけの話だ。こういう説明の仕方は、これを聞いている人々を、「人工頭脳」を考え出したのは人間頭脳だが、「人工頭脳」は何一つ考え出しはしない、という決定的な事実に対し、知らず識らず鈍感にして了う。[中略]。機械は、人間が何億年もかかる計算を一日でやるだろうが、その計算とは反覆運動に相違ないから、計算のうちに、ほんの少しでも、あれかこれかを判断し選択しなければならぬ要素が介入して来れば、機械は為すところを知るまい。これは常識である。常識は、計算することと考えることとを混同してはいない」(小林秀雄著「常識」新潮社刊『小林秀雄全集』第23集より)
実は、北野氏も小林と軌を一にするかのように、「常識」の重要性をこの本の中で強調していることが興味深い。小林が哲学的反省の末に到達した常識の動態の再評価に、北野氏も到達したのではないかと思わされる箇所を、この節の最後に引用しておく。
引用15.【人を笑わせるために常識は原理的に必要】
「よく芸人が非常識なことを言ったりやったりしたとき、芸人なんだからしょうがない、なんて擁護にもなんないことでまとめようとするヤツがいる。だけど、お笑い芸人に限っていえば、常識がない芸人は大成しないんだよ。なぜなら、笑いってのは、常識的な日常の中に潜んでいるもんだし、常識がないと笑いとヤバい発言とのギリギリの際がわからないからだ。」(142頁)
第四節:夢について
北野氏と「夢」といえば、1986年の楽曲「浅草キッド」の最後の一節、すなわち「夢はすてたと言わないで 他に道なき2人なのに」という一行を、素晴らしいメロディとともに想起する方も多いだろう。しかし、どういうわけか、この本のタイトルは、『人生に期待するな』であり、「夢」というものについて、一見すると北野氏はこの本の中で否定的な態度をとっているように見える。つまり、端的に言うと、「夢は捨てろ」と言っているように聞こえるのである。実際、以下の引用を見てほしい。
引用.16【地に足がついた本当の自分の輪郭を学習者に確認させていくのが本来の教育】
「じゃんじゃん消費して、どんどん経済成長して、みんなで豊かになろうっていう高度経済成長期の幸福論は、バブル崩壊だの、大災害だの、いろんなことがあって、いったんは否定されたはずなのだが、今も脈々と生きている。夢を持てというのも、そういう話だ。とにかく成功して、金持ちになって、贅沢できるようになるっていうのが、普通の大人が普通の子どもに教えている夢の中身だ。夢を持てっていうのは、前向きに生きろってことなんだろう。夢がかなうと信じて、一生懸命に勉強したり、スポーツに打ち込めってことだ。子どもの鼻先に夢という名のニンジンをぶら下げているわけだ。だけど、夢を持てば、誰もが一流スポーツ選手になったり、大金持ちになれるわけじゃない。努力すれば、きっとなんとかなるって、そんなわけないだろう。一生懸命やってもうまくいくとは限らなくて、どうにもならないこともある。それが普通で当たり前だってことを教えるのが教育だろう。」(225-226頁)
以下では、この「夢」というものについての両義的態度がどのように北野氏の中で両立しているのか、という問いについて考えてみたい。なぜ、北野氏は「夢は捨てろ」とも受け取られかねない発言をするのだろうか。それは、おそらくその「夢」が、あくまでも「外発的な夢」だからである。否、もっと正確にいえば、「外発的な夢」などというものはほんらい「夢」の名に値しない「紛い物」なのであるから、「夢の真贋を見分けよ、真の夢に向かうためにも贋の夢を捨てよ」と北野氏は言いたいのであろう。自分の夢だと思い込まされている他人の夢を捨てよ、と北野氏は言っているように見える。実際、引用10において、「そもそも夢を抱けとか成功しろとか金持ちになれなんて尻を叩く連中が、なんでそんなことを言うのかと考えてみれば、夢を抱いたり金持ちになろうとあがいたりするような人間がたくさんいないと経済が回らないからなんじゃないだろうか」と北野氏は述べていたことを思い出す必要がある。これを踏まえると、北野氏が、本当は、人が現在に畳み込まれた既往性という地面を蹴りながら、未来の夢を掴もうとすること自体を肯定していることがよくわかってくる。次を見てほしい。
引用17.【未来に掲げさせられた贋の夢が否定されることで現在の真の夢だけがよく見えてくる】
「本当にやりたいことがあって、頑張っているヤツを否定するつもりはない。成功しようがしまいが、それがそいつのやりたいことであれば、思う存分にやればいい。だいたいそういう人間は、夢を持てなんて言われなくてもやり遂げる。人が本当に生きられるのは、今という時間しかない。昔は夢なんかより、今を大事に生きることを教えるほうが先だったのだ。まだ遊びたい盛りの子どもを塾に通わせて、受験勉強ばかりさせるから、大学に合格したとたんに何をすればいいのかわからなくなる。夢なんてかなえなくても、この世に生まれて、生きて、死んでいくだけで、人生は大成功だ。オイラは心の底からそう思っている。」(228頁-229頁)
「人生に期待」なんかしなくても、目の前の人生そのものが、実は既に豊かであり、人にはしばしばそれが見えていないのだ。「虚構された未来の人生に期待するほど、現在の人生を我々はよく味わってみたのか」、と北野氏は問いかけているように見える。実際、ものごとにはタイムリミットがあり、未来に先送りすると未来ではもっと難しくなることも多い。そのことを北野氏は面白おかしく次のように、表現している。
引用18.【なぜ現在に目を向けることが未来を夢想することより重要なのか】
「よく「定年後に備えて趣味を持て」なんて言うよな。だけど、あれは嘘なんだよ。その趣味がいかにおもしろいかということを知るには、さすがに定年後だと遅すぎる。だって、本当の趣味というのは、会社勤めなんかをしている間に「親が急病で」なんて会社に嘘をついてまでしてゴルフや釣りなんかをすることなんだから。そうまでしてやるのが趣味なんで、定年後に何か趣味でも始めようかといったって絶対に続かないよ。親族の葬式だって嘘を言って仕事をサボって陶芸をして、できた焼き物を香典返しだって上司に渡すくらいずうずうしいことをしないと趣味なんて見つからないんだよ。」(127-128 頁)
人にもたされる外発的な夢というものを、なぜ北野氏はここまで警戒するのだろうか。それには以下のような論理があるのではないかと思われる。一般に、現代社会において、人は成長過程で「夢を持て」と言われ続ける。そうやって大人になる。それゆえ、胸を張って人に語れる夢がないことに苦しんだ者は、咄嗟に、出来合いの夢をどこか他所からもらってきて、それが自分の夢であると承認し、「これが私の夢でござい!」と嘯く。立派ではあるが、現在の自分からは離反した夢を捏造するのである。そこで北野氏は、たとえそのことが残酷に映ろうとも、現在の自己への配慮から始めよ、と繰り返す。そうでなければ、世界と私は繋留点を失ってしまうからである。つまり、私が見失われると、世界に対しての関心も見失われ、成功を手にしてもそれが自分にとって本当に嬉しいのかどうかさえ、わからなくなってしまうからである。失敗することよりも、成功を手にしているのに、その成功が本来の自分からするとどうでもいいことだから、その成功にリアリティがなくなることこそが、本当の不幸ではないだろうか。というのも、好きなことを頑張った先での失敗は、自己をより確実なものとする点で十分納得が可能であろう。しかし、好きでもないことをやり、好きでもないのだからおそらく成功
しないだろうが、万が一、そのまま成功してしまって、それをやめられなくなることは納得が難しい。失敗における自己把握より成功における自己喪失のほうがよほど不幸である。成功して何かを手に入れても、それが自分の本当に欲しかったものなのかどうか、分からないから嬉しくもない。成功が嬉しくないのと同様、失敗も悲しくない(むしろ失敗は、浮華を去って摯実に就く、つまり真の自己に復帰する契機とはなりえるから、このような状態における唯一の喜びですらあるのかもしれない)。北野氏は、このような自己疎外状態、無感動状態にならないために、自己への配慮を本書の中で繰り返し促す。
引用19.【夢より足元をみよ】
「夢を追いかけず、しっかり足元を見ろってことなんだろうね。」(77頁)
引用20.【人に夢を見させるのと足元を確認させるのとでは、どちらがより残酷なのか】
「できないものはできない、無理なものはどうやったって無理なんだけど、そうしたことをちゃんと言ってやる大人がいないんだから、残酷といえば残酷なことだ。」(19-20頁)
また、北野氏は、子どもにまずは自己の現実的輪郭を直視させるべきだという主張について、ふたつのメリットを挙げて正当化をしていると考えられる。ひとつめが、「障害を知ることで創造性が涵養される」という点で、ふたつめが、「夢の自分になってからではなく、そのままの自分で自分を肯定できる社会のほうが安心できる」という点である。どちらも一定の説得力があると考えるので、それぞれ引用しておく。
引用21.【なぜ親は子どもに夢を見させるのではなく現実を直視させてもよいのか】
「これは一般論なんだけど、人間の知恵や創造力ってのは、壁や障害があってこそ豊かに発揮されるんだろうね。分厚い壁が、その子の目の前にあれば、ほっておいてもその壁をなんとかしよう、その障害から自由になろうともがくもんだ。壁をぶち壊そうとするヤツもいれば、壁の下に穴を掘ろうとするヤツもいるだろう。壁の内側に誰も気づかなかった自由を見つけるヤツもいるだろう。知恵や創造力を使って壁や障害を乗り越えるところに、ある種の喜びがあるんじゃねぇか。」(113頁-114頁)
引用22.【誇るものなんてなくても安心できる社会の方が生きやすい】
「昔は、何も誇るものなんてなくていいって言われたもんだ。人さまに迷惑かけず、ただそのまま生きていけばいいなんてことが世の中のルールだったのに、他人と差別化して何かで一番になりなさい、なんて嫌な競争社会になっちゃった。」(75頁)
北野氏は、煌びやかな夢の世界に、経済の成長期が終わってなお期待することで、目の前の、じゅうぶん豊かになったはずの現実を味わう術を忘れてしまったということを、現代社会のさまざまな問題の根幹に見ている。では、その目の前の現実を味わう術とは、具体的にはどういう技術のことなのだろうか。北野氏が挙げている具体例と思われる部分を紹介しよう。
引用23.【他人の話が面白くないのは自分に技術がないから】
「年齢が違い過ぎるから話が合わないなんてよく言うけど、それも話が合わないんじゃなくて、話を引き出せない自分を恥ずかしく思うべきだ。年寄りとお茶を飲んでいて、「おばあちゃん、このお茶はなんて名前?」って聞けば何かしら教えてくれる。同じように、会話をしようとか、相手に対する好奇心があれば、すごくためになる話を聞けることだってある。聞かれた相手は気持ちいいし、こっちはそれまで知らなかったことを知ることができる。これは相手が小学生だって同じだ。料理人に会ったら料理のこと、運転手に会ったら車のこと、坊さんに会ったらあの世のこと、何でも知ったかぶりせずに、素直な気持ちで聞いてみるといいね。そうすれば自分の世界が広がるし、その場も楽しくなる。たとえ知っていたとしても、ちゃんと聞くって態度が大切なんだよ。」(90頁-91頁)
実は、相手がおばあちゃんであれ、小学生であれ、世間話を本気で楽しもうと思えば、組み尽くし得ない新たな側面が相手の中に見えてくることがある。見慣れた相手との会話でも、話しかけ方次第で、日常はいくらでも楽しめるのである。
第五節:書評のおわりに
この書評で私は、この本でどういうことが言われているのか、その一部を、よくほぐして、紹介してきたつもりである。北野氏は自分の思索をこれからも更新し、深化させていくに違いない。本人もそのように述べている。
引用24.【「あいつは変なヤツで何考えてるのかわかんねえ」と常に言われることが必要】
「ぬらりひょんみたいに捉えどころがないのがいいんで、そいつの芸のキモみたいなもんがみんなにバレちまったらおしまいなんだよ。あいつは変なヤツで何考えてるのかわかんねぇ、なんて常に言われてなきゃならなくて、あいつの芸はああだね、なんて解説されちゃったらもうその芸に魅力はない。生物の進化論みたいなもんで、遺伝子を組み換えて走り続けてないとダメなんだ。正体をつかませないようにして、理解したと思った瞬間には全く違う芸を見せていかなきゃ。」(138-139頁)
ここは、北野氏が、私のような人間が書く、安易な理解を警戒している箇所であるとも読み取れる。とはいえ、私はこの書評で、北野氏が金儲け主義(第二節)、機械(第三節)、夢(第四節)について論じた箇所を分析し、それらの箇所は誰にでもわかる平易な言葉で、普遍的な問いに対する一定の回答を与えていることを示してきた。冒頭にも述べた通り、これこそ安易な理解なのかもしれない。しかしそれでも、この本の魅力の一片はここまで読んでくれた方に伝えられたと信じている。
なお、最後に記しておきたい。実はこの本のなかでは、私が前節までで扱ったテーマ以外にも様々なテーマが論じられている。いくつか短文を引用しておくので、続きはぜひ自分の目で確かめていただきたい。
引用25.【神が人間を作ったのではなく人間が神を作った】
「神ってのは、人間が作り出したもんだから人間にとって都合のいい存在で、説明できない現象とか理解できない幸運や不幸みたいなものを納得させるためのツールなんだろうね。」(205頁)
引用26.【死にも適応的機能がある】
「死ななかったら人間は進歩しないだろうし、子孫を残そうなんて欲望もなくなるだろうから遺伝子が混
ざらなくなって進化もしなくなるだろう。」(188頁)
引用27.【技能実習生問題】
「前から外国人技能実習生制度にはいろいろ問題があった。」(120頁)
上から順に、神も、死も、移民も、すべて現代でこそ、なおさら重要になってきている事柄であり、考えておいた方がいい、というより、なんらかの自分なりの考えを持たずして、まともに生きていくことができないような事柄である。北野氏と同じ考えを持つべきだという話では全然ない。ひとりの思索家と向き合い、あなたとの距離を測り、あなたとの違いに驚いてほしいのである。それでは、ここまでこの書評を読んでくださり、本当にありがとうございました。
石井 恭平