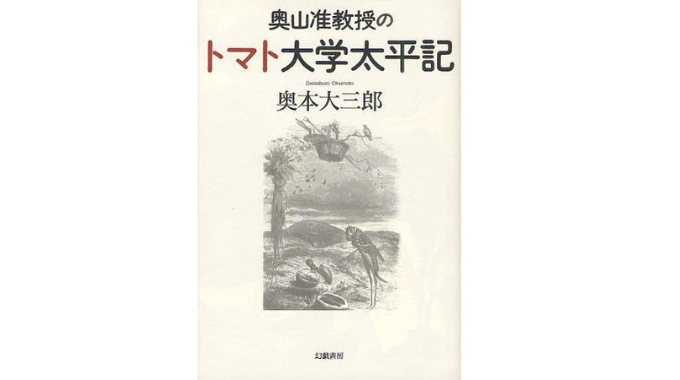評者:石井 恭平(ヴェリタス英語科講師)
第一節:とある大学教授の日常を題材にした小説
これまで私が書いてきた書評を読んだことがある方には、もはや隠しきれなくなっているかもしれない。私は天邪鬼である。これまでの人生でも、これからの人生でも、有名本の書評を書くことはできるだけよそう、と固く決意している。今回私が選んだ本も、おそらくは、あまり世間では知られていないだろう。「とある大学教授の日常を題材にした小説」というジャンルであれば、筒井康隆氏がものした『文学部唯野教授』(岩波文庫、1990年)などが有名であり、この本を挙げる人はあまりいなそうである。私は、あまり知られていない本や、読むべきでないとされている本のなかで、とても面白かったものを「ゲキシブ本」と呼称しており、こうした「ゲキシブ本」の中で、よく読むと興味深いことが書いてある部分を引用して褒めちぎるということをしばしばやってきた。私がこの本、『奥山准教授のトマト大学太平記』と最初に出会ったのは相変わらず東京都北区の区民図書館であるが、タイトルの意味不明さに惹かれて最初の章を少し読んでみたらあまりにも面白く、ネット上で191円で売られていたので、すぐに購入してしまったのである。私はいわゆる「小説」を読むのも嫌いだし、難しい「学術書」を読むのもどちらかといえば嫌いなのだが、そんな私でもスラスラと読めてしまう「学術的小説」というものが世の中には存在しており、それを読むのは本当に楽しかったのである。「学術書」と「小説」を日頃からあまり読まないのであれば、「学術的小説」はもっと読めないに違いないと思ったら、そうではなかった。このことを私に教えてくれた本がこの本である。
この本を読むと、プルーストやユゴーといったフランス文学史上の英傑たちのナマの文章に、フランス語原文も織り交ぜながら、触れていくことができ、「なるほど、こういう点に注目して読解していけばフランス文学はこんなにも面白く読めるのか」ということを学ぶことができる。ただし、「学ぶ」と言っても、堅苦しく学ぶのではない。変人教授の突拍子もないカマシや韜晦、冗談、謎かけがずっと続いていく、そんな小気味良さのなかで、気づくと知識がもはや自分にとって疎遠なものではなくなっているのである。読者は、学んだという自覚もないままに、学びの過程がもはや終了していることに気づくのである。
この物語の主人公である奥山万年准教授にそのような教育的意図や、教育方法論上の秘技の自覚があるかについてはよくわからないのだが、私はこういう教授の話し方に、研究者・教育者・対話者としての模範を見ることができるとさえ思っている。もちろん彼は、発言を読む限り、自分のことを(良き研究者だとはさすがに思っているだろうが)、良き教育者であり良き対話者であるとは微塵も思っていなさそうである。しかし、そのような自己規定に「居着く」ことで、偉そうにふんぞりかえるだけの権威者が多いことをも考慮するならば、まさにこういう自己規定を持たないで飄々としていられることもまた、良き教育者であり良き対話者であるための条件だとさえ私は言いたくなる。以下では、(1) 奥山准教授とはどういう人か、(2) 奥山准教授の言語感覚、(3) 奥山准教授の教育実践という三つの観点から、この本を分析していきたいと思う。(以下、特に記載のない限り、引用は全てこの本からであること、紙幅の都合で改行を省略した箇所があること、強調のための太字は私によるものであることを、あらかじめ断っておく。また、前回の書評と同じく【隅付き括弧】の中は、私が引用部にタイトルをつけたものである)。
第二節:奥山准教授とはどういう人か
奥山准教授は、とある国立(現在は半独立行政法人へと切り替えられた)大学の仏文科の准教授であり、研究予算の削減に苦しめられている。フランス文学を学びたいと言う学生は年々減っており、仏文学生の就職難もあり、「そのうちオーバー・ドクターの中からホームレスが出るよ」(40頁)などと言われても、特にできることはない。そういう状況で彼は地道にフランス語、そして「落日のフランス文学」の魅力を学生に伝えようとし続けるのである。その教え方については後の節で見ていくとして、このひとの人柄がたいへん面白い。以下の引用を見てみてほしい。
引用1.【奥山先生はひとりで電車にも乗れない】
「実は今日、先生はあやうく遅刻するところであった。新学期だから、とずいぶん早めに家を出たのだが、電車の中で本を読み始めて駅を乗り越した。慌てて反対ホームに来た電車に乗ったのはいいけれど、本の続きを読んでいて、またもや乗り過ごしてしまった。さすがにこれではいけないと思ったか、今度はずっと立って吊り革につかまりながら景色を眺めていたが、あいにくその電車は次の駅どまりで、ホームに降ろされてまた次を待たねばならなかった。どうもこの先生は事務能力が欠如しているのみならず、社会生活全般にわたって不適応のようである。おまけに空想癖がある。これから大学に行って大切な講義があるというのに、やっと乗った電車の窓の外に桜が咲いていたりすると、「ああ、今頃、富山か新潟の山里に行くとギフチョウが飛んでいるだろうなあ⋯⋯」と、菫や片栗の花を訪れて、ぶら下がるように蜜を吸っている、黄色と黒の小型のアゲハチョウの姿を思い浮かべる。杉林の林縁のそよ風まで肌に感じているような気になって、また乗り越しそう。まったく、ひとりでは電車にも乗れないような男なのである。」(42-43頁)
引用2.【ドルチェ・ファル・ニエンテ(甘くしてかつ無為)】
「某月某日、先生は昼頃になって起きだしてきた。実は朝の十時頃に一度目が覚めたのだけど、一言、「Liberté!」とつぶやいてまた寝てしまい、やっと今、いくら何でも、もう眠れなくなって起きたのである。「Liberté」とは、フランス語で「自由よ!」と女神に呼びかけたつもりなのであろう。休みになっていつまでも寝ていられる境遇をありがたがっているのらしい。奥山先生としては当分何もしなくていい、借金を取り立てに来る人間もいない、食い物はすぐ近所に売っていて、それを買う金もある。更に言えば、国が戦争をしているわけでもなくて、外国からの空襲もない、特高警察につけ狙われてもいない、なんとありがたい境涯であろうか、と思って「自由よ!」とつぶやき、また寝たのである。昨夜、フランス・レジスタンスの詩人の作品や、大杉栄の『獄中記』なぞを読み散らかしたのがいけなかったらしい。こういう人間を昔から「太平の逸民」といっている。」(105頁)
引用3.【鬱憤を晴らすメント】
「奥山先生は学生に「おーい、箒買ってきてくれー」と言って金を渡す。この研究室ではそれで通じる。憂いを払う玉箒、つまりお酒である。ボードレールはその散文詩集の表題を『パリの憂鬱』Le Spleen de Parisと名付けている。spleenは英語で、「憂鬱」。ボードレールの英国趣味(アングリシスム)である。それに倣ってか、Chasse spleenという銘柄のワインもある。chasseは「追い払う」ということ。先生はこうやって学生相手に酒を飲むことを「鬱憤晴らすment」と呼んでいるが、「スプリーン」とはもともと脾臓のこと。古い西洋の解剖学では、憂いは脾臓に宿る、と考えられていたのである。とはいえ、アルコールで脾臓を壊しては先生大変、などと誰も心配はしてくれない。学生も一緒に結構楽しく飲んでいる。」(51-52頁)
端的に言おう。奥山准教授は、無為を愉しむひとである。「引用1」では、窓から偶然見えた桜やそれが連れてくる想像がもう既に彼を喜ばせている。「引用2」では、切迫してやるべきことがなく、空襲も特高警察もいないというそのことを彼が無上の価値としていることがわかる。こういう態度が唐突に、そして割と詳細に描かれる章があることに面食らうひともいるだろう。しかし、よくよく考えてみると、そもそもは「妻とのんびりデートをするために仕事を始めた」はずが、「仕事をこなすためには、妻とのんびりデートに行く時間が邪魔になる」というような転倒が生じてきて、最終的には離婚したりするのが現代人である。我々は奥山准教授のスローな暮らしぶりに見習うところが多いのではないかと思わされる。
そして、「引用3」からは、奥山准教授がどんな時もユーモアを絶やさぬひとであることがわかる。全編にわたり、奥山准教授はこの調子でふざけ倒している。私もかつて、仏文科に在学していたことがあり、ブリア=サヴァラン(1755-1826)という美食家の批評文をフランス語で読んだあと、授業中に教授が「では、実際に飲んでみますか」とか言ってそのまま試飲会へと転じていったことがあるが、こういう授業が本当に楽しかった。学生と教授が和気藹々と話しながら知的な議論を進めていき、どんな話も軽視されずに、知的世界への入り口にしてもらえるのである。五感をフルに使いながら、軽妙な言葉に笑いながら、酒の肴だと思っていたものも気づくと学問の入り口だったことに気づく。「シンポジウム」の語源が酒を酌み交わしながらの知的談義であることを考慮すれば、こうした授業は逸脱的であるどころか学問の本流であると言わざるを得ない。やり方さえ間違えなければ、宴会と学問は両立するどころか相乗効果さえ生むと奥山准教授は思っているのではないか。
ただ、とはいえ、奥山准教授はいつもふざけていると見せかけて、ときどき次のような鋭い発言を行う。そのことによって、学生を一気に思考へと誘う。そうした箇所も少しだけ見ておこう。
引用4.【後発組のキリスト教は、先発組の自然信仰を利用することで栄えてきた】
「ローマ=カトリック教会は時間をかけて、古い迷信や、異教の神々が引き起こすと信じられていた超自然の出
来事への信心を、キリスト教の奇跡への信仰に変え、聖人たちへの崇拝に置き換えたんだ。復活祭なんか、冬の
間弱っていた太陽が春になって蘇ることへの喜びの祭りだったのが、キリストの復活を祝うものに置き換えられ
たわけだろ。」(138頁)
奥山准教授は「ケルト教」と「虫」にものすごく詳しい。神秘を言祝ぐ地元土着の自然信仰を「実はそれはキリスト教の神の力を授かった聖人によるものだった」という論理が包摂していくさまを彼は描き出している(同書の第四章を参照)。その章で奥山准教授は「引用4」のように語る。本論から少し逸れることを承知で、この件について少し私も自分の頭で考えてみたい。
実際、我々の日常には不思議が満ちているのではないか。金沢市で、自分も元ホームレスだった経験がある坂優(1947-2018)氏は、晩年になっても、「動けなくなるまで」ホームレス支援をしていたという。その一方で、一生かかってもひとりでは使いきれないほどのカネを持った政治家や財界人が「再分配など言語道断である!」などと高らかに言ってのける。不思議である。簡単そうなことはそう簡単には起こらず、難しそうに見えること、まず起こらなそうなことが意外にも起きている。なぜだろうか。なぜ貧しい人が他人を助けるのか。助けることを歓んでさえいる。それは、「貧しい人こそ神に近く、人はそもそも神の似姿だからであり、神の恩寵が彼に助力しているから」なのだろうか。むしろそのような理屈はこの神秘を合理化するために後づけされた理屈であって、実際にはもっと地に足のついた次のような論理がありそうである。
「誰かに助けられた貧乏人は、その誰かから受けた愛が自分の所有物によるものではないことを理解するだろう。なぜなら、所有物など彼には元々ないからである。だから、所有物なき所有者それ自体へと向けられた愛は彼に直接届き、所有物がまたなくなっても、末長く持続する。この持続的な安心を背景に彼は所有物を手放せるひとになる。それに対して、所有物を理由に愛されたことしかない人間はこの不安を背景に、所有物を手放せないひとになるのである。」
では、これで神秘の帳は解かれたのか。否である。私がいまこしらえた上記の論理でさえ、「誰かが見返りを求めずに、困っているひとをそのありのままで愛した」という最初の神秘を前提して放置している。我々が自己犠牲をするなかで、各個体に伏流するより大きな力に合流していくような歓びを味わうことがある、これを事実として私は追認するしかない。こうした利他行動とその延焼という神秘が日常のなかにはあり、それを合理化する理論装置として作られたのが神である。平たくいえば、「それを起こす神がいるから神秘が起きるのではなく、神秘が起きるからそれを起こす神がいることにされる」のである。
自然についても話は同様である。どうしたら光合成は再現でき、どうしたら細胞や脳で起きていることを解明でき、どうしたら地震を予知できるのか。重力や光なるものも正直、理解不能だが、植物はそのふたつの情報をどう処理しているのか。電子に体積はあるのか。時間と観測者との関係はどのようになっているのか。地球外で、いつもの化学反応はどうなってしまうのだろう。調べれば調べるほど謎は深まる。根本的なことは、ほぼ何も分からないまま、日々自然は神秘を次々に生成し続けている。こうした神秘を一身に担当して合理化する都合のいい神様を仮設することも不可能ではないが、まずはそのような仮設に先立って自然それ自体が神秘の塊であり、一番手の存在であるというこの順序は動かない。
第三節:奥山准教授の言語感覚
奥山准教授は、言葉に(そしてその音や語感にも)敏感である。この小説を通して彼はずっとくだらない言葉遊びをし続けようと意識していることからもそれは明らかであるが、しかし、その技術はもはや、「ダジャレなんてくだらない」と一蹴できるレベルを超えている箇所が散見される。例えば、旧約聖書の『ルツ記』から着想を得たヴィクトル・ユゴーのあまりにも美しい詩「眠れるボアズ(Booz endormi)」を解説する際、« Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth »という行の中の都市名ウルはいいとして、「Jérimadeth(ジェリマデ)」はどこを探しても見つからない。読者は一瞬戸惑うだろう。しかし、奥山准教授は、« j’ai rime à dait (=私は「デ」で韻を踏む) » が隠されていると言って言葉遊びを見抜くのである(102頁)。実際、その直後、ユゴーは「demandait」で脚韻を踏んでいる。こうした言葉遊びを笑いつつ、ユゴーの詩を解説していく手捌きは実に楽しく、詩を読むとは、実は無味乾燥なものではなく、音やリズムを味わうことと不即不離であるということが自然に読者に伝わる効果的なものとなっている。ところでこのユゴーの詩は、内容も面白い。「生の根源に立ち戻りゆく老人は、永遠の命のほうに入ってゆき、移ろいやすき日々からは離れてゆく。若者の目には焔が、しかし老人の眼には光がある」。なんとも意味深長な詩句ではないか。
他にも、奥山准教授は、次のようにして、昔の文人たちが言葉の選び方に細心の注意を払っていることを明らかにしていく。次の引用を見てみよう。
引用5.【ネルソンと東郷の頭韻による絆】
「「とにかくね、明治の人は必死で頑張ったんだよ。「皇国の興廃此の一戦にあり」って、誰の文句だ?」
「何か聞いたことありますね」
「聞いたことある、は冷たいんじゃない?東郷平八郎だよ。明治三十八年の日本海戦で、ロシアのバルチック艦
隊と戦う時に東郷元帥が発信させたZ信号旗のシグナル。このあと「各員一層奮励努力せよ」と続く。口に出し
て言ってごらん」
「口調がいいですよね」
「うん、Kou koku no kou hai kono issen ni ariと、kの頭韻が踏んである」
「これから戦争するという時に、ヨユーですね」
「余裕か。いや、逆に緊張感を高めるというか、土気を鼓舞する。これが「サーイクヨー、ガンバッテネー」じゃ、戦にならない。君ならどう言う」
「さあー」
「実は東郷元師がこれを発したのには、前例があるんだ。トラファルガーの海戦って世界史で習っただろう。英国の艦隊とフランス、スペインの連合艦隊がスペイン南西トラファルガー岬の沖で戦った。一八〇五年、日本海海戦のちょうど百年前だ。これを率いたのが彼の有名なネルソン提督。もし負ければ英国はナポレオンに征服される、という国難の時だ。まさに「皇国の荒廃⋯⋯」という一戦を前にして、ネルソン提督は信号を発する。Z旗と同じで、マストに旗を掲げて信号を送るんだよ。
England expects every man to do his duty.
どうだ、これはこのeの頭韻だ。東郷元師は英国に七年も留学して海戦を学んでいるから、当然これを知ってたわけだね」(89-90頁)
引用6.【「上田敏の秋」は「ヴェルレーヌの秋」が日本風に魔改造されたもの】
「上田敏は“秋の日の/ギオロンの/ためいきの/身にしみて/ひたぶるに/うら悲し”と訳したわけだけれど、原詩を見ると、“ためいき”とか“うら悲し”と訳すべき言葉はどこにもないね。sanglotsは、“すすり泣き”とか“嗚咽”に当たるよね。“秋のヴァイオリンの、いつまでも単調に繰り返されるそのすすり泣きのような音が詩人の心をblesserする”、つまり“傷つける”、あるいは“苦痛を与える”、というんでしょう。もっと直截に、心臓を傷つけるといったほうがいいくらいで、“うら悲し”とはほど遠いと思うよ。“うら悲し”というような、感傷的で、けだるいような、ものうい感じ、むしろ快いぐらいの甘い感じではない。もっとずっと悲痛なんだ。だから、“秋のヴァイオリン”は季節そのものの音、つまりビュービュー吹く北風の音だろうよ。それが何時までも単調に繰り返されて、止むことがないわけだ。身も心も死ぬほど寒い、やっぱり日本とは気候風土が違うんだ。でもこれをそのとおりに訳していたら、明治の日本であんなに人口に膾炙しなかっただろうと思うよ。日本的に甘く感傷的にしたのがやはり、上田敏の腕と言うべきでしょう。[…]そうそう、最後は、“ここかしこ/さだめなく/とび散らふ/落葉かな”とぴたっと止めてるだろう。この見事さ、鮮やかさ。これはまさに俳句の世界なんだ。こうなるともう、西洋の詩にヒントを得た洋食風の詩、というよりは和食だね。俳句では物というか名詞を提示して、それにすべてを象徴させることがよくあるじゃないか。たとえば“古池やかわず飛び込む水の音”という句を英訳してごらん。“水の音”で終わったんじゃ、外人は、きっと「水の音がどうしたんだ」と言うだろうよ。この訳詩でも一枚の落葉が、最後に接写レンズ的にクローズアップされて、詩人自身と秋という季節、そのすべてを象徴しているわけだ。」(190-191頁)
「引用5」は一見無関係に見えるものが「頭韻」に注目することで関連して見えてくることを垣間見させてくれる箇所である。「引用6」はさらに興味深い。上田敏(1874-1916)が翻訳した「落葉」といえば、日本でもたいへん有名な詩である。しかし、奥山准教授は、この翻訳が「死ぬ」ほど寒くなりうるフランスの秋、実際に「morte」という言葉で終わっていくポール・ヴェルレーヌ(1844-1896)の原詩が描いた秋を、「日本風の秋」へと大胆にも作り変えるなかで生まれたものであることを明らかにしていく。この箇所は、翻訳を少しでもやったことがある人なら、誰でも唸らされるだろう。翻訳という行為が実は創造行為でもあるということをこの一節を読むだけでも実感することができるからである。
第四節:奥山准教授の教育実践
奥山准教授は、本人は気づいていないようなのだが、教育がものすごく上手い。学生とおしゃべりしているうちに学生の興味をみるみる引き出す。次の一節を読んでいただきたい。例外的に長い引用となるが、奥山准教授がたったひとつの話題から様々な学問分野へと話を展開していくところを目撃していただくためである。どうか御寛恕頂きたい。
引用7.【対話型教育の模範となるような事例】
「「英語の肉の名前は、フランス語と似てますね。」
「というより、フランス語起源なんだね。」
「えー、ほんとですか。でも、どうしてなんでしょう。」
「どうしてだと思う。世界史で、ノルマン・コンクエストって習わなかった?」
「そういえば、聞いたことがあるような。ノルマン人って、ヴァイキングのことですよね。」
「そうそう、北欧のヴァイキングがね、冬になると畑仕事ができないもんだから、船に乗ってフランスに攻めて来たんだ。セーヌ河をさかのぼって沿岸の街を略奪する。いわば農閑期の出稼ぎだけど、しまいにはパリにまでやって来て猛威を振るった。連中は武力に優れているんだよ」
「ヴァイキングは、どうしてそんなに強いんですか」
「第一に身体がでかいし、もともと寒冷地に住んでいて貧しいから必死なんだ」
「でも、どうして身体が大きいんですか、食べものは貧しいんでしょ」
「それはね、“ベルグマンの法則”というものがある。「同じ仲間の哺乳類において、北に住むものほど身体が大きくなる」というものでね。トラを見ると、スマトラのトラとシベリアのトラとでは倍ぐらいシベリア産のほうが大きいし、クマだと、マレーグマ、ツキノワグマ、ホッキョクグマと順に大きくなる。これは、身体が大きくなると、体表面積が相対的に小さくなるからなんだ。寒いところに凄むものほど、体格の大きいほうが有利というわけ。北欧は寒いから人間もでかくなるんだ。それで強い。それはさておき、ヴァイキングの被害があまりに大きいんで、フランク王国の王様はたまりかねて、とうとう九一一年のこと、ノルマンディー半島をヴァイキングの大将のロロという人物に頷土として与えるんだね。このロロなんて金髪の大男で、馬に乗ると脚が地面につかえたと言われている。これが初代のノルマンディー公爵だ」
「貴族といっても、もともと育ちがいいわけじゃないんですね」
「そりゃそうさ。最初は、いわば強盗団の首領だよ。でも二、三代も経れば立派な貴族だ。そもそも、ノルマンディー半島という名前もノルマン人に由来するわけで、Normand つまりNorthman だね」
「へえ、そうですか」
「そのノルマンディー公のギヨーム、英国式だとウィリアムという男が、一〇六六年にイギリスに攻め込んで、「ヘースティングズの戦い」という決戦で勝利を収める。「バイユーのタピスリー」という織物にその様が描かれているけど、元ヴァイキングがとうとうイングランドの王様になってしまうんだ。それが、征服王ウィリアム一世というわけ。このウィリアム一世という男は、知謀に富むというか、機転のきく人物でね。イギリス征服の船から上陸した際、足がすべって腹這いに転んだんだ。「あっ、縁起が悪い!」と部下の顔が青ざめた時、悠然と立ち上がって、「なに、これから我らが物となる土地にキスしたんだ」と言ったという」
「転んでも只では起きない、とか」
「で、問題はだね、ヴァイキングがノルマンディー半島に住みついてるうちに、すっかりフランス化してしまっていたことなんだね。連中は、武力はあったけれど、文化程度は劣っていたから、言語も風習も、初代の口口から七代百五十五年のうちにすっかりフランスかぶれというか、フランス人そのものになってたんだね。それがイングランドを乗っ取ったもんだから、イングランドの宮廷ではフランス語を話すことになってしまった。そもそも形式から言うと、その英国王はフランス王の臣下ということになる。そんなわけで、英語に大量のフランス語の単語が混じることになった」
「征服された方、というか、英国の地元の人は、元々の英語を喋っているわけでしょう」
「そうだよ。アングロ・サクソン人と言われる人々は、元来の英語を使っていたわけさ。そこにフランス系の単語が大量に混じっていく。それで、英語とフランス語の語根の八割が共通のものになった。もちろん、その大本はラテン語だけどね。英語の辞典で語源のところを見ると、“ノルマンフレンチ”とか書いてあるよ」
「それでですね、家畜の名前と、その肉の呼び方ですけど⋯⋯」
「つまり、生きてる家畜の名称は、平民というか農民の言葉なわけでしょう。cowとかsheep とか言ってる。彼等が飼って世話をするんだ。だけど、その肉を食べることができるのは貴族だけだよ。だから、フランス訛りでbeef とか mutton とか言う」
「なるほど、そういうわけなんですか」
「君、焼肉好きか」
「好きですけど⋯⋯急にどうしたんです?」
「ハツ、タン、ガツ、レバなんて注文するよね、これは元々、何語かね」
「え、考えたことなかったけど、ひょっとして韓国語ですか」
「どうして」
「だって、韓国焼肉って言いますよね」
「いや、英語なんだ。ハツがheart、タンがtongue、ガツがgut、レバがliver だ。酒を飲み過ぎたりして肝臓を悪くすることを、レバイタメと言うじゃないか。」
「言いませんよ。でもさっきの英仏語の関係を適用すると、日本はアメリカに征服されたんですか。」
「君もハッキリ言うねえ。でも、まあ、実際そんな感じだなあ。日本人は肉食に関しては歴史が浅いというか、昔は内臓の旨さを知らなくて捨ててたから、“放るもんや”ってんでホルモンになったと言うけどね。“心臓焼いてくれ”、“肝臓生で食べたい”じゃ、日本人の感覚では生々しいから、わざと英語使ったんじゃないかね」
「わざとですね」
「英語が普及する前は、音読みにした。つまり、漢語風にして感じをやわらげたのかな。生きてるとウシで、肉はギュウだろ。鶏は茶褐色の羽の色から、枯れた柏の葉を連想したんだろう、昔から「カシワ」と言ってきたし、猪の肉は「牡丹」、鹿肉は「紅葉」、馬肉は「桜」と、まるで符牒だ。生き物を直接連想させることを忌んだんだろう。それまでの日本人が日常食ってたのは、雑殻を混ぜた飯と菜っぱとたくわんと味噌汁だ。」(奥本大三郎著『奥山准教授のトマト大学太平記』165-169頁)
お分かり頂けただろうか。「引用7」には、冗談も混ざっているが、実は出現順に並べてみると、❶食文化、❷世界史、❸地理学、❹進化生物学、❺語源学、❻婉曲表現といった、さまざまな学問領域を次々と横断しながら、着実に学生たちは英語とフランス語の複雑な関係を(「ただ似ている」という表面的な仕方ではなく)、根本的に理解していくのである。こういう「根源性」と「俯瞰性」を両立させた話し方のできる気さくな先生がフィクションのなかの主人公ではなく、本当にいたら、大学生活はどんなに楽しくなるだろうかと私は思わされた。
さて、本書評では、第一節で予告したとおり、三つの観点から手短にこの本の魅力を分析してきた。そろそろこの書評も終わりにしなければならない。この小説のあっと驚く終わり方などについては、ぜひ読者の皆様がご自分の目で確かめて頂きたい。
石井 恭平